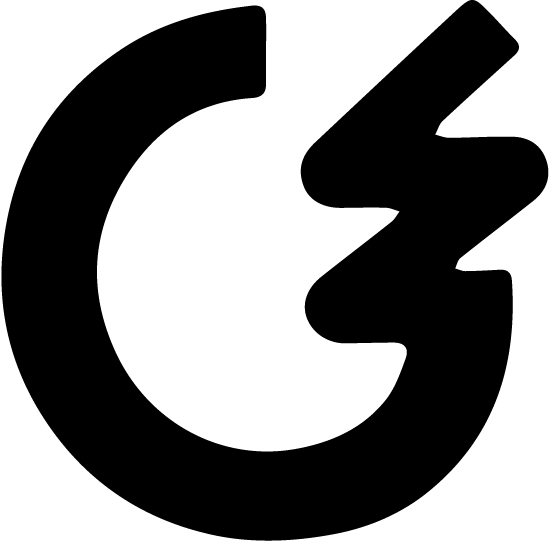荒渡巌
信州の夏は短い。多くの公立の小中学校は9月1日を待たずに始業式を迎える。朝晩の冷え込みが厳しい日も多くなり、うっかり上着を忘れて外出し日が落ちてしまえば翌日には鼻水を垂らして農作業をする羽目になってしまう。かと言えば日中の日差しはその手を緩めることなくキリキリと肌を刺す。トマトとキュウリもバテてきた。茄子はそろそろ秋に向けて枝を落とさねばならない。多くの夏野菜の収量のピークが過ぎ、夏は日に日に遠ざかってゆく。四季は巡る。私たちはただ抱かれ、そして見送るのみ。
裸足の季節を噛み締めるような今日このごろ。8ヶ月間の研修も、残すところ3ヶ月となってしまった。なんと既にその半分が過ぎ去ってしまっていたのだ。帰還の日も近い。ここらで一度、立ち止まる必要がある。振り返らねば望むことの出来なかった東京が、今度はまた鉛色の大気のドームを纏い眼前に広がっているのだ。

そもそも現代美術家の荒渡巌はなぜ農をやり始めようと思ったのか。問われる度に核心をつく様な言葉を選べないでいた。「農」をやる理由を探してみれば大体100個くらいはあって、どれもが正しいし、またそのどれもが的を射ていない。だが今ならばある程度は、その周辺だけは掘り下げて説明できるような気もする。今回は農と制作活動が私の中でどの様に交錯しているのか、少し詳らかにしてゆこうと思う。

まず自分の制作活動に関して多少の説明をしたい。昨今は漂着物や廃材、それにディスプレイという素材を用いて空間を構成し、場所や空間全体を作品として体験させるような作品を作っている。現代美術にご理解のある方にはインスタレーションと言えば事足りるだろうか。そして、この数年は野外に作品を設置することが多い。農という活動も含め、すっかり野外活動の人という印象を持たれている方もいるかとも思うが、そうした制作スタイルに至る前は実はコンピュータのディスプレイを眺め続けている様な生活/制作をしていた。

インターネットが好きだった。インターネットを徘徊して、有象無象のファイルをハードディスクにダウンロードして整理するのが好きだった。ダウンロード支援ソフトの緑色の進捗バーと残り時間を眺めているのが至福の一時だった。10代の多感な時期をサイバースペースに身を溶かすようにして送っていた私は、美術を志した際にも必然的にコンピュータを制作の相棒に選んだ。そしてインターネット上の塵芥である画像ファイルを細かく切り貼りしては構成するような画像を、平面作品として制作し始める。
深く、より深くディスプレイの奥へと手を伸ばそうとした矢先、大きく足元が揺らいだ。文字通りに揺れたのだ。2011年の東日本大震災である。
当時私は茨城県の古い木造アパートの一室に居を構えていた。外出先から戻ってみれば、棚という棚が倒れ、装飾品のいくつかが不可逆な損傷を受け、ありとあらゆるものが畳上に散乱。キッチンでは魚醤が飛び散り、ただでさえ非日常的光景に東南アジアの屋台の様な臭気までもが追い打ちをかけていた。散々な有様である。加えて町内のインフラは電気・ガスが遮断。当時制作を預けていたデスクトップのPCも当然沈黙したままである。
圧倒的無力。圧倒的孤独。たった数日間電力が供給されないが為に閉ざされてしまう生の喜びというのは、果たして何なのだろうか?年月がそんな気分も払拭してくれるのかとも思っていたが、コンピュータに触る時間は次第に減り、戸外に繰り出す時間が増えた。同時に建屋のプラグから電源を引くような美術作品に拭いきれない違和感を覚えるようにもなった。私の肉体と制作行為はケーブルレス、アンプラグドな領域へと急激に接近し、そして外気に晒されてゆく。

では、それでシームレスに「農」に繋がるのか?というと疑問が残る。いくら野外での制作を重ねたからと言って、なぜ突然の「農」?だが実は荒渡は「農」の中でも特に特殊な領域に惹かれていた。通常の農家ではなく、特別な役割を担っている研究機関を研修先としているのはその為だ。最もハードコアな農業者のひしめき合う、魑魅魍魎跋扈の跋扈する修羅道。決め手となったのは農でも土でもなく、「自然農法」という極めて限定的な概念であった。
「自然農法」というのは農の世界で一定の影響力を持つ概念で、特に田舎暮らし、ロハス、自給、エコロジー思考の強い人を惹きつけている。ただ、厳格な定義が定められているわけではなく、流派は乱立し、目指すべき状態も、そこへ至る手法もまちまちである。農薬や化学肥料を用いないというところは共通しているが、それ以外の共通点と言えば「土の持っている力を活かす」というような非常に曖昧な表現になるだろう。
対して全国の99%以上の農家はその様な回りくどい、時代錯誤的な栽培方法を採っていない。すなわち、日頃目にする、口にする米や野菜のそのほとんどが化学肥料の施用、農薬の散布という生産過程を暗に孕んでいる。

なぜ「自然農法」か?という問に応えるのはそう難しくない。改めて思い返してみれば自分の問題意識は愚鈍なまでに連続している。化学肥料や農薬の精製には莫大な電力、ひいては石油が必要となる。生産過程が見えていないだけで、実際は日々の糧の大部分が電力駆動の生産システムに依存している。そうした資材に費やされているエネルギーや、その後消費者に届けられるまでの物流を思う時、現代人が生まれながらに収容されている監獄の様なものが突如として意識されるようになる。かつて制作物から電源ケーブルを引き抜いたことと同じ様に、食材もまたアンプラグドな状態にしてみたかった。そんな食材を口にすることで、息も詰まるようなエレクトリック監獄生活に少しでも風穴を開けられるのではないか…そういう気分が確かにあった。
私達は間接的に電気を食らう。石油を食らう。そうして日々の生命を維持している。この世に生を受けた人は皆、独立した一個の主体のように振る舞うが、しかし既に、少なくともこの現代日本の都市的主体は、その生命を電力や物流の助けなしに維持できない。目に見えぬ長大な電源ケーブルが生命維持の為に無数にその身体に絡みつき、容易には外せなくなってしまっている。しかし、一度天変地異が生じれば、それらは簡単に破断し、私達はようやく己の生命の脆弱に直面することになる。

自分の作品が暗に依存してしまっている領域を丁寧に腑分けしてゆくこと。少しずつでも、そうした作業を積み重ねて制作物の強度をあげようとしてきた。農を、その中でも「自然農法」なるものを実践してみるというのは、その思想が私自身の肉体に適用されたということを意味しているのだろう。
かと言って、原始的な生き方を、プリミティブを徹底したいのか?というとそういうわけではない。社会と隔絶し、天涯孤独の生活を送りながら自己完結する美学にはそこまで欲望を感じない。誤解を恐れずに言えば、結局はただ見てみたいのだ。ディスプレイを眺めているだけでは決してたどり着くことのない風景を目の当たりにして、圧倒されてしまいたいのだ。
いずれ去りゆく土地の田園風景を横目に、私の身体を通して新たに生まれる美術作品がいかなるものであるか、今日もツラツラと考える。この地で一体何が種撒かれたと言うのだろうか。
荒渡巌 Iwao Arawatari
Twitter

1986年東京育ち。2017年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了。SNSのコミュニケーション空間やディスプレイに投影される画像がもたらす特殊な体験に傾注し、制作を行っている。サロン・ド・プランタン賞受賞。主な展示に「転生 / Transmigration 2015」Alang Alang House(ウブド)、「カオス*ラウンジpresents『怒りの日』」(いわき)などがある。若手芸術家による実験販売活動「カタルシスの岸辺」の店長でもある。2018年3月より長野県某所にて農業研修中。