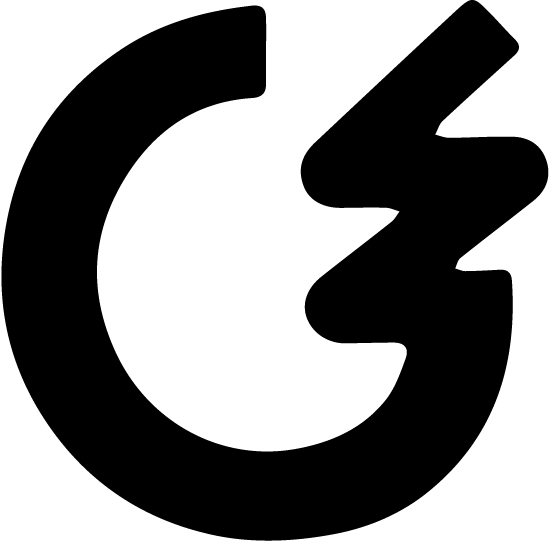渋谷の一軒家を拠点に、ジャンル横断のクリエーター集団として、音楽・ファッション・アート・テクノロジーと、2010年代のカルチャーシーンを席巻してきた「渋家」(シブハウス) 。2016年には、法人組織である「渋都市」(シブシティ) を立ち上げ、その活動は、加速度的に増進している。さまざな特異な潮流を生み出し続ける、このコミュニティのなかでも、現在、突出した存在感を見せているのが、空間演出ユニット・huez (ヒューズ) だ。2010年代のその先、不確実性の彼岸に向けて、改めて、huezの成り立ちを見つめることで、コミュニティからコミッティへと移行する同時代性を捉えたい。渋家のオーサー・齋藤恵汰の同席のもと、huez創設メンバーであるYAVAOに話を聞いた。
構成=バグマガジン編集部
_
_
グラフィックや映像の才能がなさすぎで、VJだったけど空間演出にいきついた
_
YAVAO : まず、簡単に自己紹介から。YAVAOです。美大にいたとき、大学3年のときに映像制作とVJをはじめたのですが、グラフィックデザインの才能が皆無でした。当時はモーショングラフィックとか流行っていたわけで、やっぱり映像のなかにもグラフィックの才能は必要なわけですよ。でもかっこいいのは、つくれなかったわけで、自分でVJ素材をつくったりは、あんまりしてませんでした。でも音に合わせてその場で映像をミックスしていく感覚はとても楽しくて。
ちなみにYAVAOという名前は、当時のルームメイトから「普通過ぎるから、もっとやばくなったほうがいい」と言われ、YAVAOになりました。
転機は、2012年に「REPUBLIC Vol.9」※1 で、exonemo (エキソニモ) ※2 さんと一緒にVJをしたことです。VJといえば用意されたスクリーンやディスプレイに映像を出す。つまり映像のクオリティが重要だ。僕にはそのクオリティがつくれない。とぐちゃぐちゃのコンプレックスを抱えていたのですが、exonemoさんは、人間スクリーンといって、白タイツを着た人たちに、肩に担いだプロジェクターの映像を当てるというVJ ※3 をしたんです。そのとき、VJはスクリーンに捉われなくてもいいんだ、これなら僕にもできることがあるぞ、と思って、そのまま走り続けてたらライブの演出もやるようになってました。
※1. 2008年から2012年までに10回開催された、音楽・映像・メディア・アートをクロスオーバさせたイベント。テーマは「自由な表現の共和国」。YAVAOは、2012年に開催されたVol.9とVol.10に参加。また、イベントは、2017年に約5年ぶりの復活を果たしている
※2. 千房けん輔と赤岩やえにより1996年に結成されたアート・ユニット。YAVAOは渋家名義にて「REPUBLIC」Vol.9とVol.10にて共演。Vol.10にて実施した「VideoBomber」は後に第17回「文化庁メディア芸術祭」審査委員会推薦作品に選出される (exonemo、渋家、Maltine Records 連名) 。また、これがきっかけとなり、現・渋都市株式会社 代表取締役 市長のとしくにの「インターネットヤミ市」でのメディア・パフォーマンス「インターネットおじさん」(詳細 : https://saitokeita.shibuhouse-inc.com/posts/3410213) が生まれる
※3. 渋家とexonemoとの出会いは、2011年に開催されたMaltine Recordsの主催イベント「もうなんかやけくそでサマーオブラブ」。ここで渋家は野良VJという “肩にプロジェクターを担いで映像を投射する” というパフォーマンスを実施。ここで野良VJというスタイルを目撃したexonemoが、後に「人間スクリーン」を考案し、「REPUBLIC」での共演に繋がる
_


[上] YAVAO (右), としくに (左) / REPUBLIC, 2012年
[下] 白タイツを着た人間スクリーンたち / REPUBLIC, 2012年
_
──YAVAOがはじめてクラブカルチャーに触れたときVJはどういう扱いだった?
YAVAO : はじめてVJをやったのは、新宿二丁目の「ArcH」ってクラブで、「ANSWER / リハビリ」っていう、表現難民互助会がやっていたイベントに参加したのが、はじめてでした。
_
──「VJ素材をあんまりつくったりはしませんでした」ってのは、周りのVJは素材をつくる人が多かったから?
YAVAO : まずVJの人口がそんなに多くないし、周りの人もつくってるのか、サンプリングしているのか分からなかった。でも、つくってる人も、そこそこいたはず。当時だから特にだけど、自分で映像つくってみて、だめだこりゃ、ってやっぱり止めるみたいなことはあって、つくるより、サンプリングとかしたほうが効率いいや、って思ったのは記憶にあります。
_
──どういう素材をサンプリングしてたの?
YAVAO : それは、ざっくばらんで、MVだったり、YouTubeに落ちてるやつとか、ニコニコ動画の「踊ってみた」、あと初音ミクが踊ってるやつとかダンスのモーションをCGにはめ込んでるやつ。あんまり当時は、画質にもこだわっていなかったし、まだ小屋にあるプロジェクターがHDじゃなかったから。画質悪い映像素材とかガンガン使ってた。あと、いろんなイベントを見に行ったりしてたかな。ライゾマフォロワー的な動きだったから。ライゾマさんがやるVJとかはよく見に行ってました。
_
──ライゾマはどういうVJをやってたの?
YAVAO : でかい、4メートル、3メートルぐらいの蓄光パネルにレーザー当てて、それの軌跡でVJをやるとか。その場でペンで描くみたいなノリで、レーザーで描くみたいな。
_
──そういった手法を見て、グラフィカルな素材をつくるより、音に合わせて、という方向に興味を持った?
YAVAO : それを見たときはまだグラフィカルにやるということを諦めてはなくて。映像に対してばっきり心が折れたのは25歳ぐらい。映像自体はつくろうとしていたんだけど、プログラミングとか、インタラクティブなVJみたいなものをつくろうと思っていた。グラフィックでやるということは、そもそもあんまり意識してなかったけど、自分の能力的な限界みたいなのは感じてたかな。あと強い興味がないなって感じたのもあった。
_
──でも、音に合わせるというのは、好奇心をそそられた?
YAVAO : ゲームが好きだったことも影響してるかな。音にはめてゲームをするっていう感覚に近かったから、手が楽しいと感じる、ゲーム感あったんだよね。
VJ始めて何年か経ってからDJの音をずっと聞いてると、DJがどんな気持ちなのか、想像できるようになってきた感覚があって。それまで音楽がなっている、という感覚だったんだけど、DJってコミュニケーションなんだなって。ちゃんと伝えたいメッセージみたいなものがあって、そのときのフロアの状況とかに合わせつつ、言葉を音に乗せて、鳴らしてるんだなって感覚が入ったことがあって。
そこからDJが上げるのか下げるのか、とか分かるようになった感じがある。それは、なんとなく一般の日本のクラブシーンの型みたいなのが、なんとなく自分で分かったってことだと思うんだけど。今でも海外の人のDJを聞いてると、上げるか下げるか外れることがある。日本独特の型みたいなものが体感として、落とし込まれた感じだった。
_
──DJは観客とコミュニケーションをとる。VJは?
YAVAO : なんだろう。自分かな。自分が楽しいようにVJをやるっていう基本。VJはお金もらえないこと多かったし、自分が楽しかったら、お客さんも楽しいでしょ、っていう前提でやってたかな。もちろんイベント内容によっては気を使ってるときもありました笑。好きにやるときは実験みたいな感覚は強かったかな。あんまり完成したものを見せるっていう意識はなかったから、対象は自分だったかもしれない。
_
──どういうことが実験だと思っていた?
YAVAO : さっき対象は自分って言ったけど、やはりお客さんの反応は興味深い。基本VJって興味持たれないというか、音を鳴らしている人のアイコン性のほうがVJを上回ってる。それをどうやって越える瞬間をつくるかは、意識していたかもしれない。でも20代前半は技術が足りていなかったから、DJのアイコン性を超すようなことができている感覚は全くなかった。結構惰性的にVJをやっていたかもしれない。
_
──いま、「超える」って言ったけど、「超える」ってどういうことなの?
YAVAO : 音を鳴らしてる人に、普通は目がいってるんだけど、それがスクリーンに移っちゃってる瞬間。どう超えるか。
_
──かつ、お客さんも盛り上がってる、と。
YAVAO : 盛り上がるって言葉は若干違う感じがあるけど、とりあえずDJのアイコン性を上回る瞬間みたいなのをつくれたらな、みたいなのは漠然と思ってた。やっぱりただVJをやってると悔しくなる。根本的に自分がつくったものが目立ってほしいという欲望が自分にはあると思う。自分じゃなくて、つくっているものが、目立っていないことにフラストレーションが溜まる。だからこう何か、センスもなく普通にVJをやっていると結構難しいなっていう限界は感じてたかもしれない。
_
──それは、言葉としては「敵対と調和」だと、どっちが近い?
YAVAO : 敵対。若かったから。いまは調和。こっち見ろ、みたいなのはあった。それもあって普通にVJしててもダメだって。イベント毎に映像素材つくってくるのも、ひとつの方法だったはずなんだけど。でもそのセンスないし、そもそものコスト高いから無理だなって思った。だからイベント毎に音によって映像が変わるような、ジェネのVJ ※4 みたいな、リアルタイムに生成される映像みたいなもののほうが、魅力的に思ってたかな。それで、ayafuji ※5 が渋家にきたときに誘って、huezというVJユニットをつくりました。
※4. プログラミングなどでリアルタイムに映像をつくるVJ
※5. huezの創設メンバーの一人。Robot and Computational Neuroscience。現在は空間演出ユニットとして活動するhuezだが、創設時は、YAVAOとayafuji (http://works.ayafuji.com/) の2人VJユニットだった
_
──限界を感じた、きっかけはある?
YAVAO : 段々とかな。何回やっても、DJのアイコン性には勝てないなと。そうか、今考えるとayafujiに惹かれたのって、ayafujiのアイコン性がDJを上回るからかもしれない。だから何よりも惹かれたんだな、そこに。VJだし、あんまり見えないところにいるんだけど、イベントによってはDJの隣でVJできるときもあって、そのときの身体というか、パフォーマンス性が、ayafujiはDJを上回っていたんだよ。それにすごく惹かれたってのはあるかもしれない。huezを組んだときにそれがいちばん面白いなと思った。
_


[上] 人間スクリーンとなった渋家メンバーたち / REPUBLIC, 2012年
[下] 中心でプロジェクターを掲げているのがayafuji / REPUBLIC, 2012年
_
普通という発想を捨てた
_
──そうしているうちに「REPUBLIC」に参加することになる?
YAVAO : そのときはVJをやっていても、あまり何かにならないな、という感覚になっていて。ちなみに「REPUBLIC」のちょっと前に映像で心がばっきり折れてる。MVをつくろうとして大失敗して。もう映像はいっさいやらないって決めた後だったから、ちょうど良かったのかもね。それとその時期はメディアアートへの傾倒も入っていた。あと「REPUBLIC」がVJにスポットを当てたイベントだったから、そもそもイベントのファンだったんだよね。だからイベントオーガナイザーのIshizawa ※6 さんに、別イベントで会ったとき渋家ってのがあるので、今度よろしくお願いいたします、とかって言ってた。それが影響したかはわからないけどexonemoさんが、人間スクリーンをやりたい、って言ったときに、渋家ってとこがあるらしいよ、って繋げてくれて。パフォーマンスできたのはかなり刺激になった。こういう考え方はひとつ正解でいいんだみたいな。
※6. https://www.epoch-inc.jp/member/syujiro_ishizawa/
_
──どういう考え方なの?
YAVAO : 映像を出すプロジェクターが設置されていて、スクリーンがあって、映像を出す、っていうことに捉われず、面白いことをつくろうという考え方。それは思いつくぞ、と思った。面白い映像は思いつかないけど。そもそものやり方というかプロセスみたいなものをいじくるみたいな。これだったら思いつくぞって感じが、すごい楽になった。それをやるためには、事前準備が大変で、そこは、としくに ※7 さんがいなかったらできなかった。映像作家としてだけだったら絶対にたどり着けなかっただろうなと。
※7. 現在、huezが所属する、渋都市株式会社の代表取締役市長であり、huezに3人目に加入したメンバーとして、huez活動初期から舞台監督・演出家の役割を担う
_
──なんで、メディアアートだったり、そういう手法に興味持ったんだろうね。
YAVAO : まず絵画とかに興味がもてなかった。フレームがあって、そのなかに描かれている、ってことに自分のなかで新しいと思える感覚が芽生えなかった。今は一周して、ああ、絵画面白いな、と思えるようになってきたけど。画面や額が動かないからはあったかも。物語を読み解くとか、コンテクストを読み解くとか、当時ぜんぜん分からなかった。コンテクストっていう意味が全く分かってなかった。
_
──「REPUBLIC」でやった「VideoBomber」※8 ってさ、異色というかさ。そのときにexonemoに質問したり、されたりとか、何か記憶に残ってることってある?
YAVAO : exonemoさんのブログで書かれていたんだけど ※9 、「REPUBLIC vol.9」で人間スクリーンをやって、続くvol.10でフロアに大きな布を被せようとした。exonemoの千房さんは、それが良くなるかどうか不安になってたみたいで相談したんだよね。
でも、僕それをごり押しして。exonemoさんの考え方、人間スクリーンっていうコンセプトだったら、スクリーンが動くっていうのは絶対にあった方がいいみたいな。そのとき、制作でハイになってたのかな。自分のなかでは絶対面白いはずだ、みたいなのがあって。
あと、そのとき渋家で、Fuerza Bruta (フェルザブルタ) ※10 が流行っていたのも影響した。でもFuerza Brutaを実際にやることはできないから、偽Fuerza Brutaとして、そこに布があって、スクリーンに投影するっていうのは、イケるみたいな感じがあった。
※8. http://exonemo.com/iPhone/videobomber/
※9. http://www.cbc-net.com/blog/sembo/2012/12/10/
※10. 南米アルゼンチン発の新しい体験型エンターテインメントショー。渋家では、2012年に、当時メンバーだった大輝が、NYで観劇したことをきっかけに、メンバー間でも情報が浸透し、渋家のライブ演出に影響を与える
__
大きな布による、人力で動くスクリーン / REPUBLIC, 2012年
_
──人間スクリーンっていうのは、exonemoの発案で、それから2回目、vol.10でやったときの大きな布というのは、YAVAOが提案したと。それは人間スクリーンっていうコンセプトをどう解釈してたどり着いたの?
YAVAO : 人間スクリーンはスクリーンが動くっていう考え方だったけど、そもそも空間を面白くしなきゃみたいな意識は前提にあって。面白い空間の使い方をしているリファレンスとして、Fuerza Brutaを意識はしていた。それをどうにかしてクラブの空間に落とし込めないかなって考えて、そしたら人間スクリーン的な体裁で、でかい白布イケるんじゃないのかって。なんだろうね。なんだろうな。人間スクリーンがいけるなら、手動でも動くスクリーン、イケるっしょ、っていう感じかな。
_
_
“アイコニックなVJ” となって、空間を民主化
_
──(インタビューに同席している、齋藤恵汰の方を向いて) どういうこと?
齋藤 : そもそもFuerza Brutaっていう、ニューヨークとかまあ韓国とかでツアーとかしている集団がいて、Fuerza Brutaって日本語だと ”獣の力” っていう意味なの。既存のクラブのイメージを破壊するような演出を大量に投入した2時間ぐらいのショーケースなんですよ。その “獣の力” のときにかなり使われているのが人力なんだよね。
だからFuerza Brutaのほかの演出でもそうなんだけど、例えば前から発泡スチロールのパネルがすごい勢いできて、それに体当たりして、ぶっ壊すみたいな。人が真ん中にずっと走っていて、それの周りに布が降りてきて、布の上を歩く、壁に垂らされた布の上を垂直に歩くみたいな演出とか、すごいあるんですね。
既存のクラブのイメージを壊すみたいな、方法論をわりとまあ、僕らは見て共有していたので、渋家で人間スクリーンみたいなのをやったときに、これは人力だっていうところに、たぶんかなり影響は受けたんだと思うよね。
それで、人力でスクリーンを動かすにはどうすればいいか、みたいなことを考えるようになり、その結果としてまあじゃあ大きい布に木をつけて、その木を人間が持って動かすことで、動くスクリーンを実装できるのではないかっていうふうになった、っていうことだと思う。
YAVAO : Fuerza Brutaに水槽が降りてくる演出があって、それを真似したつもり。水槽が降りてきて水が入ってて、人が滑るの、しゃーって。最初はそれができたらと思った。でもできるわけなくて、それをどうにかして再現できないかなと考えたら、お客さんのフロアの上に何かを貼らないといけないなと思って、布か。みたいな。
齋藤 : まあ言ったら、当時いろんな人がFuerza Brutaを見ていて、Fuerza Brutaを見て、影響を受けて、いろんなクラブイベントに対して演出っていうのを入れていく流れがあったんだよね。
そのなかで、うちは布っていうメディアを選択して、それを人力で動かすっていう方法論使って、さらにそこに映像を投影する、「VideoBomber」で、っていうようなある種のパッケージが一個できたと。
結局、アイコニックなDJというのは、実はもともとのクラブカルチャーからすると反しているわけだよね。クラブカルチャーっていうのは匿名性が最も重要で、DJっていうのは匿名の存在であるべきだからアイコニックなDJっていうのは、本来的なクラブカルチャーと相反するものなんですよ。それが00年代とかにばっと出てくるわけ。
_
──なんで?
齋藤 : そうね、なんでって言われると難しいんだけど、もともとクラブのステージっていうのは暗いもので、真っ暗で誰がいるか分からないところで、なんか人が動いてて、曲流してて、みんな踊ってる、ってのが既存のクラブだったんだけど。VJを入れると、どうしてもプロジェクターで投影するから明るくなるんだよね。ステージが明るくなったんだよ。それで人間が見えるようになるわけ。そうするとDJがアイコニックになるわけなんですよ。
たぶんハウスとかテクノっていうものの流行が、最終的にEDMに集結するわけだけど、EDMからでSkrillex (スクリレックス) が出てくるように、アイコニックなDJっていうのの登場が、2000年代初頭ぐらいから出てくるのね。それでさらに、それに対する反発として、アイコニックなVJ、っていうのを考えました、っていうようなストーリーだとは思う。YAVAOの言ってる、アイコニックなDJに対する、敵対する形でのアイコニックなVJっていうことを、そういうふうに整理することはできる。
つまりYAVAOは、ステージにVJが導入され明るくなった結果、DJが匿名性を剥ぎ取られてアイコニックになりました、っていうところから、さらにそれを空間全体に。匿名性と平等性だからクラブっていうのは。ステージに乗ってるやつと、下で踊ってるやつは平等だっていうのがある、ってことはステージの下も明るくていいじゃんって話だよね。それで空間全体でやろうっていうFuerza Brutaみたいな動きが出てくる。だから、ある種の民主化だと思う。
_
──クラブカルチャーにおいて、照明的な変化が生じて、人間的な側面が強まった結果、空間という視点が強まって、空間全体をどう使用するかっていう現象が起きてきたと。
齋藤 : そうだし、ステージ以外も明るくするっていう概念が導入できる程度にはステージも明るくなった。
YAVAO : 「REPUBLIC vol.10」の場合、一周して、フロアの上に布をかけちゃったからDJが見えないっていう状態をつくちゃってるんだけどね。
_

客席に覆いかぶさる大きな布 / REPUBLIC, 2012年
_
──それは、つまり客席が発見されたと?
齋藤 : そう、客席が発見された。てか、客席とステージの間に線が引かれて、その線をどうやってまた改めて壊せるか、っていうトライアルが起きた。それで、それを壊すためのある種のFuerza Bruta的な、破壊性ってのはあるかもしれない。Fuerza Brutaってステージないんですよ。その場合、真ん中には装置が置かれていて、装置が順番に出現して、装置の上をパフォーマーが歩いたりとか、走ったり、泳いだりとかする。でもそれは、パフォーマンスが終わったら、なんか隠れていくというか、片付けられる、みたいなことが起きて、そのステージとフロアの境界を、まあ分けないもんとしての、例えば布だったりとか、っていうのが出てきたみたいな捉え方はできるかな。
YAVAO : あんまり意識してないけど、垣根をなくすことがそもそも面白いという感覚がある。だから「VideoBomber」とかお客さんにガンガン当てる。照明機材のムービングを手動でやってるみたいな。でもパフォーマンス全体の良さをつくるためのバランスもあるから、DJのアイコニック性を使うこともよくあるんだけど、「REPUBLIC vol.10」のときは、結構みんなが好き勝手にやってた。お互いにプロジェクターを当てたりとかして本番も遊んでた。
_
──直感というか、頭より先に手が動くみたいな。そうやって、発想してる、ってこと?
齋藤 : 直感というかね。VJカルチャー自体が運動体としてあるから。例えばさっきのアイコニックなDJに対して、どういう人たちが出てくるかっていうと、PVを流しまくるVJとかが出てくるわけよ。それはアンセム (定番ソング) を流すDJがいたときに、そのDJが流した曲のPVを流すみたいな。これって明らかにさ、80年代とかのミュージックビデオっていう存在が出てきてからの流れを引き継いでるから、映像がどういうふうに扱われてきたか、みたいなもののアクティビズムが、いちばん有効な領域で何をやるかっていうトライアルなわけよ、VJって。
YAVAO : MVを流すのも多かったけど、YouTubeの当時の発展も関係しててリリックビデオが多くつくられていた。それでEDMアンセムのリリックビデオも結構あって、それを流すVJさんも多かった。たぶん職人的にもなれるんだよね、VJって。聞いた瞬間に次これだって、ぱっぱっと検索して、それを出すみたいな。それもタイミングに合わせて。その職人的なのは自分には合わないなと思って、僕もう、まっすぐなVJじゃなくていいやって、当時思ってたから、そっちには行かないように思ってた。
_
[後編] に続く…
_
 _
_
YAVAO / 小池将樹 VJ・LJ・ステージエンジニア。「身体的感覚の混乱」をキーワードに、デジタルデバイスやゲームシステムの企画・制作をおこなう。2011年にhuezを立ち上げた人物でもあり、現在は、huezのライブ演出の中心人物として、レーザーやLEDなど特殊照明のプランニングを担当している。 https://twitter.com/EX_YAVAO
huez (ヒューズ) 2011年結成。アート、演劇、工学、映像、身体表現、デザインなど、様々なバックグラウンドをもつメンバーからなるアーティストユニット。「フレームの変更」をコンセプトに、レーザーやLEDなどの特殊照明によるライブ演出から、МVやガジェットの制作まで、アーティストやオーガナイザーと同じ目線に立ち、その世界観や物語を重視する領域横断的な演出を強みとする。 https://shibucity.com/