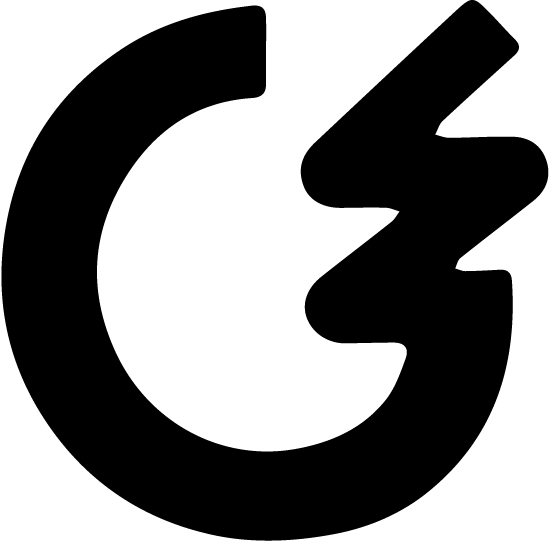第六景
東京都渋谷区南平台町
「渋家」
アリの巣のような渋谷の地下通路を抜けて地上に出る。
西口の横断歩道を渡って首都高の下を潜ると、桜丘一帯はフェンスで囲まれていた。仮囲いの向こうにもちろん人気はなく、いくつもの重機が佇み、全ての建物の窓には田と×を合わせた形にガムテープが貼られている。そう、桜丘は大規模な再開発の真っ只中なのだ。

 photo by Mai Shinoda
photo by Mai Shinoda
中学生の時分からよくこの辺はぶらついていた。渋谷の「表」たるスクランブル交差点の方も好きだったが、国道246号を隔てて、楽器屋や小さな飲食店が多い桜丘も、渋谷の「裏」という感じで気に入っていた。それにこのエリアは、シェアハウス「渋家」に出入りしていた頃、メンバーとたまに散歩に来ていた。渋谷とは思えないくらい閑静で、「奥渋」松濤の高級住宅街ともまた違う、庶民的な街並みが心地よかったのだ。
 photo by Mai Shinoda
photo by Mai Shinoda
旧東横線を跨いだ駅南の「渋谷ストリーム」は、見知ったチェーン店の寄せ集まった「複合施設」として既に聳え立っている。雑居ビルの背中が犇めく脇にちょろちょろと流れ、無骨だった渋谷川も、これ見よがしにビュースポットが用意され、電飾が吊り下げられて、なかなかに無残だ。桜丘もまた、ビルの底に沈んでいくのだろうか。……
 photo by Mai Shinoda
photo by Mai Shinoda
桜丘の「丘」を登った南平台に、「渋家」はある。
2008年に始まってから、実はすでに10年以上続く「渋家」は、シェアハウスであり、コレクティブであり、アート作品であり…とにかく勝手にやっているのだから、オルタナティブであることに相違ない。かくいう私も、5人の立ち上げメンバーの内の1人だった。池尻大橋のアパートの一室から始まり、駒場の一軒家、恵比寿のマンションと、渋谷の周縁を経巡って引越しを繰り返し4軒目、地下1階から3階、屋上まである南平台の一軒家が、現在の物件である。
そんな渋家前にて、このプロジェクトの言い出しっぺであり、作者であり、初代代表の齋藤恵汰と合流する。今も渋家は、20人前後が住んだり利用したりしているそうだ。メンバーは新陳代謝が盛んで、二十歳そこそこの人たちが多く、その日はちょうど地下のクラブスペース「クヌギ」で新年会のパーティが開かれていた。
 photo by Mai Shinoda
photo by Mai Shinoda
どこか空いている部屋でインタビューを収録するつもりだったが、どの部屋も、若い子たちがゴロ寝していたり、ゲームをしていたり、PCを開いて仕事していたり、地下からはズンズンとDJの音が響いてくるし、完全に所在無く、三十路を超えたわれわれ初期メンバーは、逃げるように渋谷の街へ出ると、結局マークシティ裏の大衆居酒屋「山家」に腰を落ち着けたのだった。
 齋藤恵汰 photo by Mai Shinoda
齋藤恵汰 photo by Mai Shinoda
「ランドアートをやりたかった」と齋藤は口火を切った。
なぜ渋家を立ち上げたのか、予備校の美術系クラスで出会った者を中心に、大学に自由な空間が無いと見越して、自分たちの溜まり場をつくりたかったからだと私は記憶するが、意外にも齋藤は父の思い出を語り出した。「うちの親父、東大でサークルをやってたんです。実はそのサークルが今でも続いてて、どういうサークルかというと、ヨットを維持するサークル。当時、ヨットで太平洋単独横断を成功させた『太平洋ひとりぼっち』(堀江謙一)という本が人気で、30人くらい集めてヨットを買ったらしいんです。それが神奈川のヨットハーバーに今でも浮かんでる。そのサークルのメンバーたちが、年に何回かうちに集まって飲むの。ヨットを維持するという人間関係。何かを維持する集団というだけで一つの形式になるというのは、子供心に面白いと思っていました。」
「これを僕は後に、ランドアートの作家であるロバート・スミッソンの《スパイラル・ジェッティ》だと思ったんです」と齋藤は続ける。「《スパイラル〜》って中心点があってフラクタルになってるでしょ。そして、造った時代よりも水位が上がってるから年に何回かしか顔を出さないんですよ。しかも、そこにいろんなアーティストが関わることによって評価されていったという運動がある。ランドアートという運動として、サークルがあって、その中心にモノがあるという構造。それらを知った時、“こういうことやりたい!”と思ったんです。」
 photo by Mai Shinoda
photo by Mai Shinoda
中心のモノ=家と、円形/同好会としてのサークル=コミュニティ、そして運動=ムーヴメントという構造は、なるほど渋家にも敷衍できる。では、そもそもなぜ渋谷という「ランド」にこだわったのか。齋藤は「一番土地代が高いから」とあっけらかんと語る。「不動産屋に行って住宅の家賃の相場を聞いたら、山手線で渋谷を中心に下がっていくと言われた。じゃあ一番高いところにしよう、と。」 もちろん、渋谷はユース・カルチャーにおける象徴的な街でもある。「日本の問題にまで話を広げてしまえば、日本は地方が疲弊してるし、もっと言えば地方に戻っても文化的なものを享受するのはインターネット以外ではほぼ難しくなってきている。そういった状況がある時に、現実的にそれを回避する1番の方法は“住むこと”なんですよ。渋谷に住んだら何か面白いことが起こるかもしれない、だから住んでみよう、となったんです。」
 photo by Mai Shinoda
photo by Mai Shinoda
そうやって渋谷周辺から出発した渋家(当初は中島らもの小説にちなんで「ヘルハウス」と呼ばれていた)は、先述した通り、数年の内に引越しを繰り返すことになる。「最初は池尻大橋の2DKのアパート。金銭的にそれぐらいしか借りられなかったんです。一年半くらい住んだんですが、メンバーが増えて部屋が狭くなったことと近所からの騒音苦情で、駒場の一軒家に引越しました。その二軒目の家で重要だったのが、『渋家トリエンナーレ2010』だった。」
『渋家トリエンナーレ2010』、何を隠そう、私が企画した展覧会である。「メンバーの中島晴矢がその家全体に布をかけた。僕がすごく覚えてるのは、“お前がロバート・スミッソンなら、俺はクリスト&ジャンヌ=クロードだ”と言ってきたこと。しかもそれは、漫画『すごいよ!マサルさん』(うすた京介)の家に布がかかってるというギャグでもあった。“パロディのパロディ”というのがステイトメントだったんです。」
たしかに、忘れかけていたが、シミュラークルとして布かけを行なったのを思い出す。「そもそも渋家がランドアートの“パロディのパロディ”だった。もともとランドアートは、反ギャラリーシステムのためにアメリカの砂漠などで行なわれていたもの。それを東京都心に持ってくる。しかも新しく何かを作るのではなく、物件というレディメイドを使う。ここにパロディの二重性があった。だとしたらそれに対抗できるのはクリストとマサルさんを経由した二重のパロディであるというコンセプトで、僕はそれが面白いと思ったんです。さらに、ちょうど『横浜トリエンナーレ2010』が開催されていた。まだあまり芸術祭がない中で『横トリ』が目立っていて、だとしたら僕らも『渋トリ』をやるべきだろう、とそこもある種パロディ化されていた。それらのパロディを全部一緒くたにまとめる形で、布をかけた家の中で芸術祭をやろうとしたんです。」
 photo by Mai Shinoda
photo by Mai Shinoda
そう、とにかくそういったロジックで、布をかけた家の中での芸術祭を企画したのだ。だが、布をかけた直後、大家や警察などに注意を受け強制退去を余儀無くされてしまう。「二つ目の家に布をかけたら家がなくなった。象徴的だったのは、そのタイミングで『東京アートポイント計画』(アーツカウンシル東京)のリサーチとして岸井大輔さんが来たことです。東京のアートスポットを探すプロジェクトなのに、行ってみたら場所がない。でも、落ち合った居酒屋に次から次へとメンバーがやってくる。そこで岸井さんは“あいつらおかしいです”という報告をした。最初の話に戻せば、モノとサークルがある状態から一ヶ月間モノが無くなった時に、モノを探している人たちがリサーチに来るという面白い交差があったんです。しかもそこにコミュニティはあった。」
「基本的に僕はアートって、“宝探し”か“かくれんぼ”か“追いかけっこ”だと思ってるんです。現代アートはこの三つしかない」と齋藤は持論を展開する。「“宝探し”というのは、新しい技法や物質なんかを探し出してくること。“かくれんぼ”というのは、表から見るとあるものにしか見えないのに、実は全然違う意味を隠しているような象徴主義的な作品。“追いかけっこ”というのは、ひたすらリサーチして、こんなものを追いかけましたというプロセスを全部見せるものです。」 かなり大雑把な括りとはいえ、言われてみればそんな気もしてくる。「家が消えた瞬間の渋家には、ものの見事にこの三つが同時にあったんです。つまり、新しい物件という宝を探していて、次の家を追いかけるプロセスを全部見せていて、なおかつみんな家がないからどこかに身を隠さないといけない。だから、むしろあの一ヶ月間だけが作品だったのだと言うこともできるかもしれません。」
 photo by Mai Shinoda
photo by Mai Shinoda
“追いかけっこ”で言えば、ちょうどその頃がSNSの黎明期であり、Twitterなどを多くの人が使いだした時期だった。家がなくなったので探す、というプロセスをSNSで全て晒し「バズった」ことによって、渋家が見知らぬ他者に認知されていったのだ。「そこで“情報爆発”が起きたよね。一月後にようやく借りた恵比寿の家で、初日から三日間、24時間解放して念願の『渋家トリエンナーレ2010』を開催したら、アーティストや文化人も含めてたくさんの人が来てくれました。」
その家から、ネットレーベル「Maltine Records」主催のtomadを中心に毎週パーティが開かれたり、後にテラスハウスで芸能界デビューするちゃんもも◎がメンバーに加入したりと、ある変化が起こってくる。また、起業をした渋家は名目上とはいえ会社になった。「実は三つ目の家で発生したのって、“ビジネス”と“音楽”と“芸能”なんです」と、齋藤はまた大鉈を振るう。「それまでアートとしてやってきたものが、ある一定以上のものになると資本主義のリアリズムに到達するわけですよ。すると、ビジネスや音楽や芸能が到来する。当然僕らは社会人としてド素人だから最初は扱い切れない。音楽は無料配信・無料パーティだし、芸能は地下アイドルだし、会社は立ち上げたまま三年間休眠するわけです。」
 photo by Mai Shinoda
photo by Mai Shinoda
結果的には半年強で再び引越すことになる3軒目の家だが、私が記憶に残っているのは何と言っても2011年3月11日の東日本大震災だ。「ちょうど三つ目の家で様々なものが到来する浮き足立ったタイミングで、同時に震災が到来し色々な現実が家に降りかかってきたから、僕はむしろ冷静でいられました。震災後に4つ目の家を借りて、もともとあったアートというものを使い、それまでに出来てきた色々なパズルのピースを、今度はそれこそキュレーションしてブリコラージュし、一個の彫刻にしていかなければならないという状況になるわけですね。そしてひたすら彫刻し続けたら、多くのアーティストが作家として活躍し、地下がクラブスペースになり、本物のアイドルがデビューし、『渋都市』という会社が回るようになった。」
この現在の家は既に9年目を迎えるが、多様に拡散しているように見える今の渋家という運動を、齋藤はどのように捉えているのだろう。「でも、中心にアートの問題系があるから、多分それを適切に処理しないと崩れるんですよ。アートって基本的に最先端じゃないですか。だから最先端のことをやっているという部分が失われたら、当然もたないんです。渋家って結局、最先端のことを維持するための装置ですから。」
最後に渋家の今後の展望について聞くと、「続いてくと思いますよ。もう畳みようもないしね。一回つくっちゃった作品って、もうどうしようもないじゃないですか」と齋藤は笑った。
 photo by Mai Shinoda
photo by Mai Shinoda
設立11年目を迎える渋家は、最も混沌としてオルタナティブなプラットフォームのひとつとして、既に渋谷という地に充分に根を張っているように見える。常に変化し続けるこの街の只中で、奇妙で異質な中心点が存在し続ける未来を思うと、これからの渋谷も決して悪くないような気がした。
 photo by Mai Shinoda
photo by Mai Shinoda
<渋家 shibuhouse>
<著者プロフィール>

(c)Taro Inami
中島 晴矢(なかじま はるや)
Artist / Rapper / Writer
1989年生まれ。主な個展に「麻布逍遥」(SNOW Contemporary)、グループ展に「ニュー・フラット・
webサイト