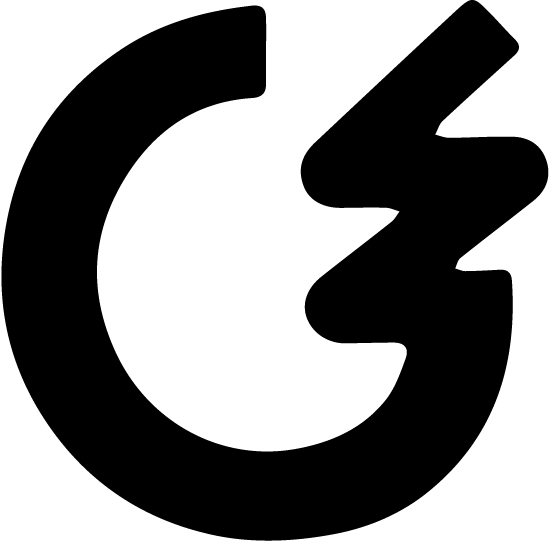著:荒渡巌
研修生活も早、二ヶ月が過ぎた。ビニールハウスで毎日のように面倒を見ていたトマト、ナス、かぼちゃといった夏野菜の苗たちも畑に飛び出してからしばらくが経つ。カッコウの鳴き声が聞こえるようになったが、相変わらずヒバリの求愛の歌も続いている。ツバメも巣作りが一段落したのか、以前ほどはつがいでの共同作業を見かけなくなった。春を締めくくる一大イベントである田植えもまた滞りなく済んだ。梅雨入り前だというのに半袖でないと外作業が怠くなるような気候が続いている。上着を脱ぎ捨たのを忘れ、あとで圃場に取りに行くこともザラである。夏の訪れの近いことはすれ違う人々の服装でなく己の肉体で否が応でも感じる。
夏が来る。夏野菜を畑に出す。が、その前に畑が空いているのが勿体なくも感じたので葉物を播種することにした。
葉物というのはレタスだとか小松菜だとかほうれん草だとか、葉っぱをメインに食すものの通称だ。トマトやナスといった実もの野菜が播種から収穫まで半年近くかかるのに対し、葉物は比較的はやく収穫できる。例えば小松菜は品種にもよるのだが、なんと最短30日程度で収穫できてしまう。しかも雪の降らない温暖なところならほぼ一年中栽培できる。場所も時期も選ばない小松菜は本当に凄い。家庭菜園を始めるというと敷居が高いと思うが、小松菜をやってみない?と言われれば何となく出来そうな気がしないだろうか。今すぐにダイソーで種と土を買ってきて、小松菜を育て始めてみるといいと思う。プランターなんて要らない。買ってきた土の袋の上部を切り裂き、底に排水用の穴をあけ、そのまま種を撒いてベランダにでも設置し、土がカラカラにならないように毎日水をあげておけばそれでよい。栽培期間が想像以上に短い野菜があるということは皆さんに広くお伝えしたいことだったので、とりあえずここまで読んでくれれば最低限の仕事は出来たかなと思う。

では、「間ビ記」を開始する。
なんのことかというと「間引き」のことである。辞書的には「植物を栽培する際、苗を密植した状態から、少数の苗を残して残りを抜いてしまう作業」を指すらしい。葉物を栽培する上で決まってやることになっているのが間引きだ。
そもそもなぜ間引きをせねばならないのかというと、まずは全ての種が発芽するわけではないということがある。また生育が悪かったり、病気にかかり収穫に至らない個体もある。それに加え、生命力の乏しい双葉の幼い時期を乗り切るには密植していた方が良い。ということで作物にも品種にもよるけれども、種が多く撒ける作物ならば撒くというのが慣例になっている。
多めに撒き、そのまま密植状態で生育してゆくとどうなるかというと、葉と葉が重なりあって影になった方は日の光を求めて妙な生育をして形が悪くなるし、養分を奪い合って互いの健康な成長を阻害してしまう。そういうわけでやはり、人間の都合で間引く。

その間引きを遂に自分の畑で決行する日がやって来た。今まで研修先の作物に対しては何度か行った行為ではあるが、主体的に撒き、出芽させた作物に対して間引きを行うのは初めてのことだ。冒頭にも記したが、夏野菜の前に「小松菜」、「ほうれん草」、「春菊」といった葉物を植えておいたのだった。こういったものは、二度三度の間引きをして適正な間隔に調整するというのが教科書的には推奨されている。
双葉が出揃うと一度目の間引きを行う。葉が隣の双葉と重なりあっているならば抑えられている方を抜く。指でつまむのがやっとの大きさの双葉である。気を抜けば二、三株ごと一気に引っこ抜いてしまう。そうしてそれぞれが過不足なく受光できるような間隔を作る。それを一定の期間ごとに繰り返す。
「群」でしかなかったそれらは、成長とともに、また「間引き」という行為を通して個の連なりとして再認識されてゆく。一つとして同じ育ち方はしない。同じように見えても茎の細さ、葉の大きさ、しなり方に個性がある。そうして個性が出てきた作物は、それまでの作業の対象物としての認識を転覆させ、突然に一つの独立した生命として対峙してくる。
隣り合うそれらは、兄弟や姉妹のように仲良く寄り添っているようにだって見えてくる。生育の良い株の周りに密植している様子は、棟梁を慕う徒弟たちのようにも、教師のもとに集う学生達のようにも見える。そこからどんな白昼夢だって描ける。しかし指で地面で引っ掻くだけで、そうした物語の萌芽もまた失われ、畝は「生産」に特化した無機質な姿に落ち着く。全く虚しいような気持ちになる。
遂には口内で咀嚼され滅ぼされる生命に対して愛情を抱くというのは、よくよく考えれば非常に成立し難いことが分かる。農業技術というのは、その生命力をより多く収奪することが目標とされている。研修の始まった頃、「あまり植物に気持ちを傾けてしまっているようでは農業はできない」と指導員に口酸っぱく言われたことを思い出さずにはいられない。
美化も美談も忍び込めないハードな現実がここにはある。私達は殺さないで食うことなど出来ない。植物は確かに生命なのだ。彼らも種を残すためにその生命を全うしようとしている。タンポポの花を切り落としたことはあるだろうか?切り落とされた花は、しばらくするとあの見慣れた綿毛へと変貌する。刈払機で畦草をなぎ倒し終わって一服する際、刈払機の通り道を振り返ってみると、先程まで花をつけていたタンポポがもう綿毛となって地面に点在している。なんという執念だろうか。ゾッとする光景である。視界の隅々まで生命の活動に覆い尽くされていることが恐ろしく、その濃さに逃げ出したいような気持ちにもなる。

菜食主義者達は動物に対する愛護精神と厳しい戒律を自らに課してはいるが、しかしやはり植物を人間の都合で収奪する。人間が“この肉体”に縛られているかぎり、「不殺生=死」であることからは避けられない。生きとし生きるものは殺し、奪い合う。そこに善悪はない。生きることと殺すことは頭で理解していた以上に渾然一体としている。
都市に暮らしていると、どうしてもそうした気分が希薄になってしまう。東京のあの現実感のない浮遊感というのは、殺生を締め出してしまったところにあるのではないだろうか。視界に映らぬ人間や、動物や、植物を、どれだけ奪い、損ね、殺しているのか、想像の糸筋さえもつかめない。その暗黒から抜け出したいからこそ自分は都市生活のバックヤードたる農の現場に飛び込んだのだった――

当初の予定よりも随分と内省的になってしまったが、とにかく間引きに直面するとかなりの緊張感があったし、これは多くの人に直面してもらいたいシーンではある。なので、気が向いたら小松菜でも作ってみて欲しい。気が向かなくても作って欲しい。分からないことがあれば気楽に連絡してくれて構わない。己の手で種を撒き、間引き、選抜した株を育てあげ、刈り取り、食らう。都市に追放された殺生をこの手に取り戻すのだ。その叛逆の一歩をダイソーから踏み出すというのは、いかにも私達らしいことではないか?
荒渡巌 Iwao Arawatari
Twitter

1986年東京育ち。2017年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了。SNSのコミュニケーション空間やディスプレイに投影される画像がもたらす特殊な体験に傾注し、制作を行っている。サロン・ド・プランタン賞受賞。主な展示に「転生 / Transmigration 2015」Alang Alang House(ウブド)、「カオス*ラウンジpresents『怒りの日』」(いわき)などがある。若手芸術家による実験販売活動「カタルシスの岸辺」の店長でもある。2018年3月より長野県某所にて農業研修中。