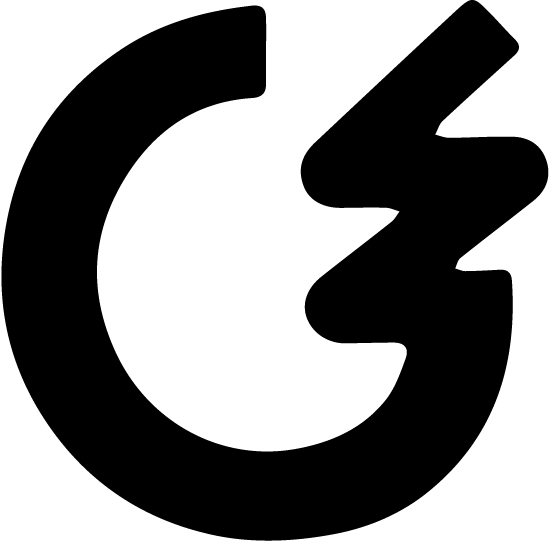今回のテーマは身体改造とオカルト。その筋では超有名人のケロッピー前田さんの『クレイジーカルチャー紀行』が刊行予定です。ケロッピーさんは名前こそかわいらしいですが、意図的に身体を加工する人たちを国際的に取材してまわっている人物。もっとも彼は表面的に身体改造を物見遊山してるだけではなくて、そのいっけんクレイジーな世界の奥底にある「ふつうの身体」というイメージを掘り崩そうといういろんな人の試みから何かを浮き彫りにしようとしている感じがします。
『ダークウェブ アンダーグラウンド』
1月刊行の本でもうひとつ気になっているのは、『ダークウェブ アンダーグラウンド』。「インターネットにはなんでもある」とかよく言われますが、たとえばグーグルで検索しても出てこない情報はたくさんあります。ある種のポルノとか違法性のある薬物、危険物などについてはふつうに簡単にググっても到達できないんですね。そもそもネットに上がってない場合もありますが。それはさておき、近年もりあがった仮想通貨騒ぎでもときどき光が当てられたのが、そういったちょっとググっただけでは出てこないネットの深部あるいは暗部があります。違法性が高いというか犯罪や詐欺などに関わる情報を、インターネットを使ってやりとりする領域、それがダークウェブです。
『リーグ・オブ・エクストラオーディナリー・ジェントルメン:センチュリー』
昨年、第2巻が刊行されて僕も大いに感激した『プロメテア』。その作者は『ウォッチメン』や『フロムヘル』でも知られるアラン・ムーアですが、そのムーアのもうひとつの代表作がこの『リーグ・オブ・エクストラオーディナリー・ジェントルメン』。日本現代SF史に残る名作にして、早逝した伊藤計劃の構想を円城塔が完成させたという逸話も熱い『屍者の帝国』の公式元ネタ本のひとつに挙げられているシリーズでもあります。その本作の完結巻がこれ。今年2019年は先述の『プロメテア』も完結巻になる第3巻が刊行予定だし、日本語圏におけるアラン・ムーア需要のひとつの区切りになる年ということなのかも知れません。
『海底二万マイル』のネモ船長をはじめとする虚構世界の有名異端者たちがイギリス諜報部の命を受けて、ノーチラス号に乗って世界を巡り怪事件を解決するという怪奇活劇と書いてしまえばそれまでですが、19世紀的レトロ趣味や厭世的な世界観に裏打ちされた各設定など読みどころは満載になること間違いなしです。
12月の新刊
『オカルティズム』
昨年最終月に刊行された書籍、なんといってもこの大野英士『オカルティズム』が素晴らしい。残念ながら英仏をはじめとする欧米のオカルトが中心になっており、日本でのオカルティズム 的な系譜までは辿られていませんが、古代からはじまり中世のキリスト教世界での各種神秘主義の展開、ルネサンスにおける古典主義に付帯する魔術再興、そして近代の政治的な右翼と左翼それぞれのオカルトの受容にいたるまで、どこを読んでも面白い。世界には秘められた部分があり、なんらかの方法で人はそれを読み解くことができ、あまつさえそれを操作することもできるという願いや信念の系譜であるとも言えるでしょう。
本書と同日に発売された同じ講談社メチエの『記憶術全史』では、この書かれたものとしての世界を、記憶という人間の内部に書き込むための技術、つまり世界を神によるデータベースとして捉え、それを人間の脳内というアナログで想像的なデータベースへと移植あるいは移設するための変換術の歴史をまとめたもの。併せて読むと興味深いです。
ドン・デリーロ『ポイント・オメガ』
アメリカ文学最重要人物のひとりによる150ページくらいの小品。ヒッチコックの名作映画『サイコ』を超低速で再生して上映する実在のインスタレーション『24時間サイコ』を美術館で鑑賞している男の描写と、その描写に挟まれるように構成された本編での、30代の映画作家と彼の被写体にならないかとオファーされている老人とのやりとり。老人は作者デリーロと同年齢で、かつて湾岸戦争の際には有識者としてペンタゴンに招聘されたこともあるという。映画作家と老人は、ある砂漠のなかの家で日々を過ごすが、そこに老人の年若い娘が現れ、そして突然すがたを消す。この様子を淡々と描くのが本作です。2010年に発表された本作は、おそらくアセンションというニューエイジ的なジャーゴンを意識しています。女の人が突然すがたを消す、という現象は村上春樹の諸作品を引き合いに出すまでもなく文学上ではよくあることなんですが、死体が残る殺人や自殺、病死ではなく、肉体ごと消え失せるというのはどういうことなのでしょうか。作中人物にもそれをどう捉えていいかは示されないわけですが、しかしたとえば『24時間サイコ』は美術館の開館時間よりも長い再生時間があり、上映されている出来事の一部始終を鑑賞者が見届けることはできません。これと同様に、ある人は他の誰かの一生のすべてを見届けることはできないし、ましてどんな人も惑星や宇宙、もしくは単に人類というひとつの種の始まりと終わりを、見届けることはできないのです。書籍のタイトルであるポイント・オメガとは、北京原人の発掘に関わったティエールドジャルダンという修道士が、いつか宇宙の歴史の終着点(ポイント・オメガ)が訪れるとき、それはあらゆる知性の最高到達点であり、それまでに失われたすべてが記憶や回想の中に文字通り「再生」されるだろうと述べたことに由来します。オカルトに詳しい人ならばアカシックレコードのことを思い浮かべるかもしれませんが、最近のバズワードでいえばAI技術が発達して人類の脳の活動を超越するシンギュラリティ仮説がこれに近いと言われています。壮大すぎはするものの、楽観的な展望を与えてくれるこれらの言説に対して、デリーロはどこか寂寞とした(まさに砂漠的な)センチメンタリズムでもって、取り残される側の心象を描いたのかもしれません。
『資本主義の歴史 起源・拡大・現在』
20世紀後半に人類を核戦争の脅威に陥れた東西冷戦は、一般的に共産主義と資本主義の対立だと考えられています。その共産主義側の理念的な象徴であったソビエト連邦が20世紀末までに崩壊し、ソ連と並ぶ大国とされていた中国も表面上は共産主義でありながら実質的には資本主義化するという状況で迎えられたのがこの21世紀です。これをもって、現代世界では資本主義が全面化していると考えられていますが、では現在の資本主義はいつ頃から「この」体制なのでしょうか。それを知るためには、資本主義にはどのような種類があり、どのように進展してきたのかを知る必要があります。
本書はドイツを代表する歴史家のユルゲン・コッカによる人類史的視野での資本主義の歴史をまとめた一冊。とはいってもこの種の本にしては驚異的なまでにシェイプアップされていて、扱われている時間的スパンは長大なのに本の厚さはごくわずかなもの。全体を薄くするために各部分については記述が浅薄で雑になっているところが多々ある感じがしないこともないのですが、それでも資本主義の歴史を概観するというとりあえずの目標を本書で一旦達成してから、気になった部分については他の本で深めていくというスタンスで向き合えばいいんじゃないでしょうか。
『パンダ探偵社』
昨年末に刊行されて話題になった作品です。難病もので先輩後輩の探偵2人組、しかも変身譚。難病と探偵的2人組を描いた作品といえば最近では、SFサイコサスペンスとでもいうべき『LIMBO THE KING』が熱いですね、他人の夢の中に精神的な癌のようなものが生まれる「眠り病」というのがあって、罹患者の意識というか無意識にマインドダイブする話。この『パンダ探偵社』の世界では、動物や植物に変身してしまうという病気が流行しています。主人公はいつかパンダになってしまう。第1巻の時点ではパンダの能力が描かれているわけではありませんが、その主人公を学生時代の先輩が探偵社の助手として雇う。見た目がパンダになりかけてる主人公は見た目が目立ちすぎるから探偵はあんまり向いてないんじゃないかとか思うのですが、この探偵社は主人公と同じような変身病罹患者に関する事件を扱うので、患者の気持ちがわかる主人公が雇われているのはそういう理由であると説明されたりしています。
なおマンガでは古くから「マンガの神さま」こと手塚治虫が生涯のテーマとして「メタモルフォーゼ(変身)」を抱えており、『火の鳥』をはじめとしてそのテーマに踏み込む作品を残していることもあり、変身ものは実はマンガというジャンルそのものに関わるものだといえます。生身の人間が生きる「人生」の出来事を、紙の上で再現するということは、そもそも紙の上の線を「変身」させているとも言えるわけです。演劇や映画ではどうなんだ、という話になるかもしれませんが、生身に拘束される舞台芸術はさておき、最近のCGの発達めざましい映画の世界でももっぱら「変身」といえばもともと紙の世界で展開されてきたアメコミのスーパーヒーローものが中心的であることを考えれば、やはりマンガが特権的な位置を与えられているということは言えると思います。もっとも、アメコミ原作の映画でもいわゆる変身をするのはX-MENとかの一部のシリーズにとどまっているわけですが。
ともあれ、日本のマンガでは手塚治虫的な、あるいは手塚もマンガ化してるカフカ的な不条理な「変身」と、マンガよりも子供向けおもちゃ産業と結びついた石森章太郎以降の「仮面ライダー」シリーズがあるといえます。『パンダ探偵社』は仮面ライダー的な可逆的な変身ではなく(仮面ライダーも、変身可能な身体に改造されてしまったわけですけど)、カフカ的な不条理な変身を描いた作品です。これに類するマンガとしては最近では渡辺ペコのそのまんま『変身ものがたり』や、浅見ヒッポ『花落としのいつか』、昆虫好きで学者肌というまさに手塚治虫直系ともいえる都留泰作の『ムシヌユン』など傑作揃いです。変身ものというとちょっと違うかもしれませんが五十嵐大介『ウムヴェルト』もこの集合に加えていいかもしれません。ともあれ、変身譚というジャンルそれじたいは文学の世界で連綿と受け継がれてきた伝統ではあるものの、やはり変身の様子を視覚的に提示できるマンガというジャンルは変身ものととても相性がよくて、今後も傑作が生み出されていくのではないでしょうかとか言いつつ、今年2019年最初の汽水域の旅を閉じようと思います。次回の更新でとうとう終わりですね。楽しみにお待ちください。では。