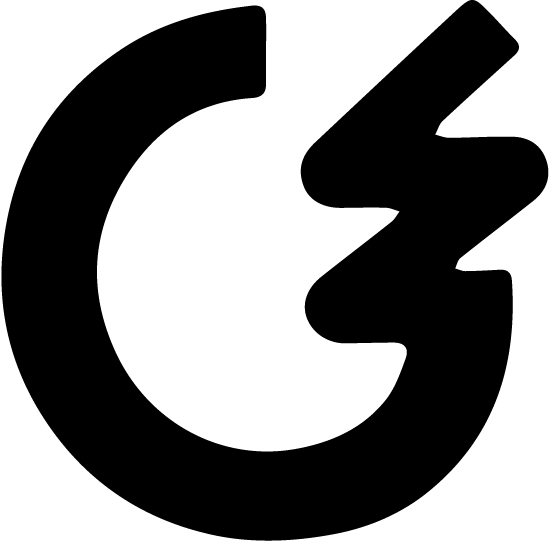ゆうきくんとは知り合って10年ぐらいになるけど、いまだによくわかっていないことのほうが多い。彼の「ほんとうのところ」をつかみあぐねている人は少なくないと思う。ぼくはその代表みたいなものだ。もっともそれが数時間のおしゃべりで明らかになるほど、石田祐規は凡庸な人物ではないのだけど。たとえこのささやかな試みがそううまくいかなかったとしても、かまわない。そうしたいのだと思わせてくれる魅力が彼にはあるのだから。なによりこの社会には目眩や輝きをもたらせてくれるものがすごく足りないと思いませんか。
――お久しぶりです。
お久しぶりです。最近は大きな展示もイベントも予定してないので、なんでも自由にお聞きください!
――ぼく個人としては、過去の展示のインタビューを読み返してみて、ゆうきくんが、そういえば東京にもどってきてから何をしているのかが気になってたところでした。仏教用語に往相・還相という言葉があって、ぼくなりに要点をまとめると、「あちら」の世界で経験を積んだ人が、やがて煩悩の渦巻く「こちら」に戻ってきてその考えを皆に還元するというものです。かねてから、東京に「戻る」って表現は独特だと感じていたんだけど、まさにこの数年でその「戻り」を経験したゆうきくんにその経験を聞いてみたくて、今日はおよびだてしました。まず沖縄にいったのは2016年の3月24日だよね。そのあたり、東京や渋谷、シブハウスを離れようという契機があったの?

うん。単純に東京に飽きてた。前のインタビューでも答えたけど、東京に8年いて全然お声もかからないし、どうにもならなさみたいなのに絶望していたから、沖縄に行ってそこででやるべき自分の仕事として、休憩することだったり写真をとることだったり、友だちの太加丸と本をつくることだったり、それからナハウスを盛り上げることっていういくつかの仕事をして、東京にもどってきた。というか、改めて東京にも役割があるんだな、ということを感じています。でも、東京に戻ってきてからもう1年経ったんだね。
――沖縄に行こうと思ったのは、急に決まったの? それとも徐々に?
行く前の10月から徐々にだね。それまでは沖縄に住もうなんて1ミリも考えてなかった。2015年10月22日に手塚太加丸が遊びにきたんですね、シブハウスに。「人が少ないからナハウスを3月末でやめようと思っている」という話をしたときから、おれのなかでナハウスに対して、何かしたいな、責任をとりたいなという気持ちがあった。そこから行こうと決めたのは1、2ヶ月かからなかったと思うんだけどね。そのへんは詳しく覚えてないな。出発2ヶ月前には決まってたと思う。送別会を3つハシゴした記憶があるから。
――行く直前だったと思うんだけど、Facebook に印象的なエントリをアップデートしてたよね。相当なエネルギーを使って書いたんだろうなって気が当時はしたんだけど、あのときの心境はどんな感じ?
覚えてないんだよなー、あんまり。たしか、そのあと直後に会ったよね。あれはやはり自分の認識できない怒りだったんだと思う。だって、そうじゃん、あのときは本当に大変な時期なわけで、この状況でみんなと5年後を迎えたくないって思いが当時あったわけ。なのに、みんな、シブハウスでやるプロジェクトだったり企画に一切モチベーションを示さないでいたからそういうところに憤り、焦りを感じていたのかもしれない。でも正直、そんな覚えてない。それに、何かの区切りや節目で文章書きたがりだと思うんだよね。東京離れるということに対してしんみりした気持ちだったんだと思う。離れるってなったら東京を見る目はかわってくるしね。
――ちなみに全文引用してもいいですか笑
いいですよ。
Yuki Ishida
February 27, 2016 · Shibuya, Tokyo ·
ぼくは仕事ができない。仕事の引継ぎがむつかしい。もはや引継ぐ必要性があるのか?と疑い始めてしまうほどヤバい。「渋家」というアートプロジェクトが2008年にはじまって2016年まで8年間、なんらかの役割を演じたり演じなかったりしていた。
出会った頃の Keita Saito は渋家―当時はヘルハウス―のことを「小説」と称していたし、それから「美術作品」になり「演劇」になっていった。チームの運用としては最初期からずっと民主主義を採用していて、多数決をとったり、誰かが勝手に決定するということはなかった。それは19歳のぼくにはとってかなり刺激的だったし、いままでの怠惰な自分が少しは変わったと思う。結論が出るまで話し続ける。途中で眠くなって寝ちゃっても、起きたらまだ議論が続いているから参加できる。学校にしろ、職場にしろ、民主主義が採用されている場ってぜんぜん無くて、当時の自分には衝撃的だった。
そこには役割っていうのは無くて、よく勘違いされる。家に来る人が「掃除や料理って当番とかあるんですか?」と質問されるのが逆に驚いてしまう。人間は本質的に怠惰だな、と感じる。ルールや当番を決めて、実行する(まったくもって民主主義的でない!)そしてルールを守らない人を”悪いひと”として糾弾する。このようなことを渋家では一度も見たことがない。そこが「渋家」を信頼できるところでもあるし、自分が8年間も居続けられた理由でもあると思う。
メディアで報道されたとおり渋家の3大ルール(?)である「ルールを作らない・多数決をとらない・避妊をする」は知っていると思う。当時は頭の中が「???」だったのだけれど。今なら分かる。この3つのルールが言っているのは「怠けるな」ということなのだと。楽なほうへ楽なほうへと流れない。ルールを作れば簡単に”悪いひと”を作ることができるし、楽だ(しかも早い!)。この渋家3大ルール(?)を維持するのは大変だしデメリットもある。どっかのアメリカの大統領が言っていた「民主主義はスピードが遅い」と。ご多分に漏れず、渋家はいつも遅いのです。この遅さに耐えられない人は渋家を去っていく。
話は戻るけど「家のことって誰がやるんですか?」という質問にはいつも「気付いた人がやる」と答えています。これ、冗談じゃなくてマジです。一番面倒くさい方法をとる。ずっと気を張って「気づく人」になる必要があるので、ただただダルい。めんどい。疲れているときは「気づいてない人」のフリをするときもある。申し訳ない。でも、気付き続けないといられない場というのはやっぱり刺激的で好きだ。
「コミュニティにはニートが必要だ」と誰かが言った。誰だっけ? みんな言ってるのかな。まぁいいや。ニートは必要です。コミュニティ全員が忙しいと物事がうまく回らないのは実感としてあると思う。なんかの本で書いてあったけど、会社の窓際族と呼ばれる人たちを一斉にクビにしたら、残った人の人間関係がギクシャクして潰れたという話は、おおむね本当だと思う。「この人、なんもやってないじゃん!」というのは何かしら見えない仕事をしているのできちんと”気づく”ことが大事だね。それでも日々の仕事が忙しかったりするとなかなか気づけない。それを解決することがニートの仕事。
ぼくはお腹が空くとつらい。これは残念だけれど本当だ。だからいつもニートから逃げていて、すぐに労働をしてしまっていた。時間を切り売りしてお金に変えて、後には何も残らない。それでも3度のチャレンジがあって今ここにいる。一度目はITの会社を辞めてニートをした。でも6ヶ月でまた働き始めてしまった。2年後、また仕事を退職してニートに宣言しようと決めた。でも9ヶ月したら今度はゲーム会社で働き始めてしまった。今回はニート3度目の挑戦。去年の1月からニートを継続しているので、ニート14ヶ月目だ。労働にかまけて「見えていなかったこと」にようやく気付き始めた。
渋家における仕事は少人数に偏っていた。これに気付けなかった自分を恥じた。ニートになれば時間はたっぷりある。家のことはおおむね引き受けられたと思う。それまでは渋家に頼りっきりだったなー。それでも家のことを集中しているとナレッジが溜まってくるのでこのまま渋家を抜けてしまうのは少々もったいないと思う。
(まったくもって文章が下手で申し訳ないのだけれど、ぼくは4月から沖縄に移住します。このことは最初に書いておくべきだった。許せ)
ぼくの言いたいのは「ニートにもノウハウがある」ということ。
ようやく言いたかった主題に戻ってくることができた。コミュニティにいたことがなかったらニートという役職を知らなかったし、わからないことばかりだったけどニートができたとぼく自身は勝手に思っているので、渋家から抜ける前にノウハウを継承したいと思ったんです。でも、この文章の1行目に書いてあるとおりぼくは仕事ができないので、仕事を引継ぐということが分からない。ビジネス書によくかいてある「すぐ手を出してしまって部下が育たない悪い上司」状態なのです。人生で引継ぐという概念がなかったし、想像したこともなかった。こんなことを新年から考えていたら、あっというまに2月が終わりそうになっている。もう時間がないし、このノウハウを伝えるニートも渋家にはいない。だから今は「引継がない」という決断に心が傾いている。人間は怠惰だから。でも、残った人が1からこの知見を発見していくのはなかなか時間がかかると思うのでどうにかしたい気持ちもある。
翻って、ぼく自身は引継がれるのが嫌いだ。「渋家22日ホームパーティ」を 山口 としくに さんから引継いたときも3ヶ月ぐらいはあーだこーだ言ってきて正直ダルかったw 俺のやり方でやらせてくれよ! こっちで勝手にノウハウ積み上げていくからさ! というワガママで傲慢なところがある。これはもう引継ぐ資格が無いと言っていいでしょう。
そこで、これを読んでいるみんなに提案なんだけど、こういうコミュニティ事に興味のある人、4月から渋家に住みませんか? できればニートを希望したいのですが、アルバイトをしていてもいいです。いかがでしょうか?
連絡おまちしています。めんどうな引継ぎはありません。
当方、仕事できません。
――では、沖縄にいって実際どうだった。最初の1週間覚えてる?
人すくねーなーってかんじ。がっつりいたのは俺と高橋くんの2人。あの広さの物件に2人だけは相当寂しかった。
――そこから人は増えた?
うん、増えた。
――それはゆうき君も関わっているコト?
うん、飲み会をしたりとか、呼んだらとにかく喋って、「ナハウス住まない?」、「住みたい人紹介して」ってコミュニケーションによって淡々とネットワークを広げていった。東京ほど登場人物が多くないからさ、沖縄って。東京だと「Twitterでは知ってるけど、会ったことない人」って100人、200人ざらにいるじゃん。沖縄だとそのへんが1/4ぐらいの規模だから、Twitterみつけたら今度会えるみたいな距離感だし。
――想像してたとおりの暮らしだった?

うん。どうだろ。想像どおりなのかな、わかんない。あんまり想像もしていなかった。冒険にでかけるイメージ。ゼルダの伝説的なバイブスだね。
――はじめから期間は決めてたのかな?
それは決まってた。1年。
――何しに行ったかを改めて聞かれるとなんてこたえる?
ナハウスを維持したかった!
――そのモチベーションってどこから湧いてくるのかな。すごく利他的な動機にうつるんだよね。
え、利己的よ、おれのなかで。そもそも東京でもオルタナティブスペースってどこでも産まれては消えているじゃない。全然淘汰に任せて消えちゃえばいいって思ってるんだけど、ナハウスだけはどうしても失いたくなかった。年に1回ぐらいは遊びに行っていたし、あの時間・あの場所がかけがえのないものだったから。そこはすごい利己的なんですよ。俺の旅行先を失いたくない。ナハウスがなかったら俺はもう沖縄にいくことは出来ないから。
――コミュニティが回るようになったのは、軌道に乗り始めたのはいつぐらい?
9月かな。行ったときにどう進めていくか考えたんだけど、3ヶ月ごとに区切って4タームで考えていこうかなって。3ヶ月ごとに何が起きたかを自分の中でふりかえって、次の3ヶ月の行動を決めようって思ったのね。とりあえず最初の3ヶ月は、いるよってことを示さないといけないから、とにかくいた。Twitterで宣伝したりFacebookページを整えたりした。家がものにあふれていて、散らかっていたので、太加丸と相馬と協力して車出して、ゴミを清掃工場に持っていて、4回にわけて運んだのよ。服とか誰のかわからないものが200着以上あったから。そんなのを思い切って捨てた。界隈のグループラインがあったから週に1回は飲み会やるよって案内を投げてたりしてたかな。実装的な部分でいうとそれぐらいだと思うんだよね。あとおれの醸し出す空気感だったり喋り方だったり、言語化できない部分の仕事もあっただろうけど、そこはよくわかんないかな。
――いちばん人が多かった時期はどれぐらいの出入りがあったの?
その年の11月は個展もやったし、50人ぐらい出入りしてたかな。2016年の12月だね。沖縄から40、東京から10ぐらい。
――前回のインタビューは個展の直前だったよね。
展示の2週間ぐらい前から。11月の半ばぐらい。
――いまさらだけど、個展の感触はどうでした。たとえば……売れた?
作品は2枚売れたし、ZINEも捌けたので、トントンかちょい黒字ぐらいにはなったかな。

――自分のなかでの経験値としては印象に残っていることはある?
自分のなかで否定してた真っ当な写真を紙に印刷し、等間隔にきちんと並べるみたいな、メインストリームの展示は初めてだったからなあ……。
――逆に、今まではどうだったのかしら。
今まで個展なんてしたことなかった。グループ展として「イケイケハッピーハッピー写真ニューイヤー」はやったけど、あれはグルーヴ感をだしたかったから人を集めただけで、個々の写真はどうでもいいというか、写真のスキル自体はみんなそれなりにある人だったから、そこまで展示空間にコミットはしていなかった。エリアだけ割り振って「あとはご自由に」ってかんじ。あれに関しては展示と言うか、展示をどこまで流通させることができるのかみたいな自分の中の実験だったからね。
――話は戻るけど、その上で、自分の個展をやってみてどうだった。
人であふれかえっていることが自分の中でのご褒美でした。
――来た人がどう感じるかは副次的なもの?
そうだね、言われてみれば。そうかもしんない。人が集まることが大事なことだと思っているから、展示はそういう手法になっちゃうし。
――この写真を通して何かを感じてほしいとか、たとえば、リビングに置くことによってその人の生活がこうなってほしいとかは考えない? それってすごく商業的な考えかな。
それももちろん大事だけど、今のところ興味ない。リビングに飾るような写真は撮ってないし。
――沖縄で個展を開催したことには何か意味付けはあったの?
いろいろとあったじゃない、当時。友だちが死んだりとか、みんな低収入で働いているとか。もういんじゃないかって思った。もうリミッターを外してもいんじゃないかみたいなことを言いたかったんだけど、それを言うと政治的なので、だったら「仕事をやめても、あるコミュニティから離れても、俺はこういうふうに楽しくやっていますよ」というのを、あの写真群全体からじんわりと感じてほしかった。そのためにだったら罪を犯してもいいじゃんという気持ちがあったから「完全犯罪」というタイトルをつけたんですよ。バレなければいいと思ってたからね。「死ぬぐらいだったら罪を犯せ、そしてそのお話に俺を誘え」って宣言だったの、あの展示は。ネタバレしちゃうとね。本当は個展ぐらい一回ぐらいやっとかないといけないとっていうキャリア的な話もあるし、やったことなかったから一度やっておきたかったという好奇心もあるし、展示をした場所を友だちとイチから一緒につくったという文脈性があったりね。そもそも最初は壁もたってなかったんですよ。ぜんぶ茶色の壁だった。それを木で壁をつくって、友たちとペンキで真っ白に塗ってから数日乾かしてから写真をはるみたいなそういう物語もあったりして、あの場所に愛着があった。ぼくの初個展をあの場所でやることで、ぼくがやりましたという歴史性も、お互いにとってハッピーにできるという確信もあったかな。
――その完全犯罪というコンセプトは成功した? 誰かに届いたという感触はある?
うーん、ないんじゃない。写真をみて影響をうけるほどヤワな人間はそうそういない。やはり評論家の翻訳が必要だろうなとは思う。石田祐規という作家は何者なのかという。ぼくが評論家でもすごい難しい。なるべく客観的にいるようにはしているんだけど。
――たしかにある程度付き合いは長いけど、一貫性がないところが一貫しているというのがぼくの印象かな。
そうだね。
――表現者としての印象を一言でステイトメントにしようとすると難しいかも。
それはまさにぼくの目指しているところだからなんだよね。写真集とかって見る? たまに見るんだけど、数ページでもう飽きちゃって閉じちゃう。それはなんでかというと、一貫したルールによって写真集の1ページ目からそのルールが守られているから退屈で閉じちゃう。けど、マーク・ボスウィックみたいに、一貫したルールはあるんだけど、それが何かよくわからないとつい最後のページまでみてしまう。
――でも、それを目指すのってすごく危うくない? いろんなところに誘惑の落とし穴があるわけよ。「これでやればいいんじゃない」って。
うん、うん、ありますね。それは自分の性格にすごい助けられていて飽きっぽい性格なんですよ。だから、写真を長く続けられている。あんまりもっていかれない。ファッション写真や広告写真、ドキュメンタリー写真なんかにね。そういったカテゴリーに全然振り回されないし、そういった写真をとることもあるから、形にするときにはそういったものとかプライベートの写真とかをぜんぶ混ぜて本にするのが現在のスタイル。

――沖縄でやったことは他にはある? コミュニティをつくったこと、展示をやったこと、他には…?
友だちを結婚させました。沖縄で一昨年、その前とoddlandというイベントを有志で無料野外フェスをやってたのね。コザ運動公園を1週間借りて、2万人ぐらい動員するイベントを入場料無料でやっているんですよ。沖縄に住む前に旅行で3週間ぐらい沖縄に行ってたんだけど、それの1回目にちょうど遭遇して、その話を増沢大輝とか齋藤桂太にしていて、ちょうど大輝がキッチンプロジェクトという飲食店をはじめるプロジェクトをしていたので、手始めに次の年のイベントにスタッフ用のケータリングを手作りでやろうって話にハイナさんというイベントに関わっている人につなげて、2回目のスタッフ用のお店を出したんですよ。そのときに、大輝くんと水上が出会い、仲良くなるのを横目でみてた。そこで大輝と出会って結婚したので、ぼくが仲人できる唯一のカップル。
――東京でも人間関係のハブになっていることが多いよね。
そうそう、だから東京と沖縄をつなげる仕事をしていた。
――それはどうして? 外からみるとそれも利他的な行動のようにみえるんだよね。
そっか、そうみえるのか。それはぼくは友だちのことが好きだから。東京の友だちはみんなすごく苦しそうにみえた。それで沖縄の人には失礼かもしれないけど、東京の人がいつでも沖縄に逃げられたらいいなと思っていたし、逆に沖縄の人もいつでも気軽に東京にこれたらいいなと思って、シブハウスとナハウスの連携関係をつくれるように動いた。
――そのときのゆうきくん自身の苦しさはどこにいたんだろ。東京にいたときのしんどさ。
なにしたらいいのかわかんなみたいなことかもしれない。なにしても評価されない空間だった。鯉がいないかもしれない池にずっと餌を毎日あげつづけている感覚。頑張っても「写真界よくなっていく手応えがないぞ」みたいな。写真界側からもずっと無視されている感覚はあって。それは今もそんなに変わってないんだけど。ちょっと元気を取り戻してもう一度やってみようって気持ちではある。
――人をケアすることによってバランスをとるタイプなのかな。
というか、他者の存在が自分の作品制作に関わってくるから、いいコミュニティ、いい場所をつくるというのはめちゃくちゃ重要。友だちも場所もなかったら、写真とれんしね。だから、農家が畑を耕すのとまったく変わらない行為。本業ではないけど得意になってしまった。ただそれだけなんだよね。東京に戻ってきたら意外とそれが求められて。
――そこで本題なんだけど、東京に2017年4月に戻ってきたわけじゃない。で、この1年間どうですか。かつてと違ってみえることってある?
うん、東京が相対的に捉えられるようになったのはすごくお得だと思った。東京だと些末なことでみんな困っているけど、沖縄だったらこう解決するよなってのが頭にあるだけで、東京の人が当然そう動けるわけじゃないんだけど、その解決策をいくつか知っているだけで、やりきれない状況も精神的負担がなくなる。たとえば、高いところに手がとどかないときに、沖縄だったら木で足場をつくる。東京だと歩いていける距離にホームセンターがないから木材や釘がカンタンに手に入らない。100倍ぐらい沖縄に比べて入手の難易度が高い。なので、東京の人だとAmazonで脚立を買うんだけど、そういう方法もあるから、いざ手元になにもなくても、今はこの問題をみんなで解決しているけど、ひとりぼっちになっても全然問題ないという謎の自信みたいなものはある。DIYの精神や助け合うことの大切さ、心強さを沖縄ですごく経験した。沖縄で展示やるときに「手伝いにいくよー」って言った人が実際に手伝いにきてくれる。それって東京の展示のときにはなかったことだから。電話で何日も前からアポとってお願いしないと人を集めることができない。みんな沖縄だとふらっと来てくれるんだよね。あれを経験しているかしていなかでは人を信頼する気持ちが変わってくると思う。コミュニケーションの話ばっかりになっちゃったね。
――たしかに……。ゆうきくんにとって表現者としての道って優先度は高くないの?
いや、表現の優先順位はすごい高いし、失ってはいけないものなんだけど。俺の中で常にやってることだから、今この瞬間だって仕事をしていると思っているし。たとえばあなたが将来どうにかなったときに「ああ、この人の10年前の写真持ってますよ」ってきちんと的確に写真を提出できますよ、という仕事があって。そのためにさらに仲良くなっているみたいな手続きだったりする。演劇の演出家みたいなもので常に仕事はしている。
遠い未来に、この近辺の人間関係を可視化するときの資料だったり道具だったりになったらいいな、というイメージでやっている。ステートメントにも書いてるけど、100年200年たったときに写真見返したときに「この人は楽しい人生を送っていたんだなぁ」と未来の人を勘違いさせたいと思っている。これって作品じゃねーのか。でも。活動、アクティビティか。
――ワークって感じじゃないね。アクティビティだね。それを聞きたかった。アクティビティとしての石田祐規は何をしているか分かっているんだけど、ワークとしては何をしているのかな。
ワークとしては写真人口を増やすことだと思います。基本的には。
――それは前から? 戻って来てそう思ったの?
それは前からかな。イケハピのときからそうだったけど、日本の写真界が元気ないなというのはあって、問題を突き詰めて行くと人口の少なさみたいなところ。野球場って田舎でもそこら中にあって少年少女だったり社会人野球をやっているわけじゃない。そういうレベルから10万人100万人といるからプロ野球の100人が食えているわけで、そういう第一層・第二層・第三層とか土台の部分を大きくしていきたいと思っている。

――スマホの登場で写真をとることはすごくお手軽になったし、instagram のおかげで1億総フォトグラファー社会になってるわけじゃない。そことは断絶があるの?
あると思う。写真を撮ることは写真の仕事ではないからね。行ってしまえば、俺の作品は誰か別の人に撮らせても成立するじゃないですか。他の人はそうはできないというか。撮影という行為は写真の仕事における1割ぐらいの割合なんだよね。残りの9割の仕事がぜんぜん残っている。
――9割も? 詳しく教えてください。
簡単な技術的な面で言えば、たとえば今日撮った写真を10年後に即座に出せますか? となったとき一般の方は出せないんですよ。データが失われていたり、HDDの奥底に眠っていたりするから。でも写真家はきちんとアーカイブして、いつでも取り出せる。アーカイブだったりバックアップというのが写真家の仕事の30%~40%を占めている。そこに金かけてるし、俺も相当そこにお金を持って行かれている。
――フォトジェニックなものを撮ろうという思考が社会においてすごく支配的じゃない。ゆうきはそういう撮りかたをしないじゃん。つまり、卑近な例をあげるとパンケーキを石田祐規は撮らないわけ。人物の写真が多いこといつもにびっくりするんだよね。びっくりというか、文脈がないと分からないものを撮るじゃん。ものに甘えてないというか。パンケーキはパンケーキそれ自体でお話が成立するけど、そういうのは撮らないよね。
うん、そもそもあんまり考えないかな。そういうのはけっこう前の段階で卒業してしまったというか。いろんなゲームボードがあって、そのゲームからは降りてしまっただけ。自分はたまたまハイコンテクストのものに興味があったというだけかも。
――沖縄に行ったからといって何か変わったわけじゃない?
うん。自分は変わってないよ。環境が変わった。生きやすくなった。いつでも沖縄に行けるという関係値があるあら、アポなしで明日沖縄に行っても、今の生活の延長上が送れるっていう自信があるわけ。服も展示作品も沖縄に置きっ放しだしね。
――東京に戻ってきて1年たって、エネルギーも蓄えて来たころだと思うんだけど、今後の展望はどういうふうに見据えてる?
アクティビティと見分けがついてないんだけど、まず一つ目は若手写真家と引き続き繋がっていこうということ。それは自分が若かったときに年上の写真家に全然サポートしてもらえなかったという苦しい思い出があったから、自分が28歳になったので、今度は18歳以降ぐらいでサポートを必要としている写真家っていうのと繋がっておこうという。いい大人になるための活動をひとつしています。
二つ目としては引き続き恋人の写真を撮っています。それは去年の2月に「家族設計」という台湾でやった個展として、恋人の写真だけをひとまとめにできたので、相当ピースが埋まって来たなというところ。交際が始まってもうすぐ9年になるのかな。それが一区切りつくのかな、つかないのかなといったところ。すごい恥ずかしいけど、付き合った直後ぐらいに「写真を撮らせてください」って長文メールを送ったんだよね。もう内容も覚えてないけど、ジョンレノンとオノヨーコを例えに出して説明してた気がする。あと1年とちょっとでそのプロジェクトが10周年を迎えるので、それをどうにか形にしたいです。
三つ目の仕事としては、東京と沖縄を行き来したことで生まれたカップルそして家族ができて子供ができたというのがあるので、その家族を次は10年ぐらいのスパンで撮ろうかなというラインを走らせようかなという感じです。
――息が長そうな仕事だね。
写真って一瞬だし、簡単だからこそ、めちゃくちゃ時間かかるのよね。最低10年は撮ってないと人々を驚かしたり圧倒させたりはできないと思っているから。
――それはどうして?
「何かこういうものを作りたい」という圧力や「すごいセンスで撮りました」といったものが自分には無いから、時間というパワーを利用して、上乗せして人を殴りたいからみたいなところはあるのかもしれない。センスのいい写真を撮ったりとか、テクニカルで凄い写真を撮ったりとかはできないので、なんかしょうもない写真がポンとあるんで、そこに物語だったり文脈だったり歴史だったりをどんどん服を被せていってゴージャスにしていって一等賞になりたいです、という感じです。それが写真の歴史に貢献できると思っているから、写真に出会うまではすごい人生退屈だったしね。ここまで自分を助けてくれた写真だからこそ、こんどは僕が写真を助けてあげたい。っていうなんか気持ち。それくらい大きな目標を立てておかないとマジで人生退屈になっちゃうんで、大きなプロジェクト1個・小さなプロジェクト3個、合計4つぐらいを回しているのが自分の中で調子がいい。
――あれなんだっけな、小さい女の子が表紙で、その子の成長をずっと撮っている写真集あるじゃない。
はい。それは川島小鳥の「未来ちゃん」ですね。
――たとえばああいうものはどう評価しているの? 僕は素養がないからパッと思いつくのがそれくらいしかないんだけど。川島小鳥さんはやりたい? って聞かれたらどう答える?
うーん、なんて答えたらいいのかな。やりたいことのひとつ、ロールモデルとして見ているから。もう3年前になるのかな木村伊兵衛賞を獲って。で、まだ30代だから、まだまだ若い人なので、これからどういうキャリアになっていくのかはまだ予測不能なので、あまり語る対象ではないというか。でも、語る準備をしなくちゃいけないなと感じています。
――どう差別化したい?
あー、そういう作業ね、自分の苦手なところなんだよなぁ。やはり人間性みたいなところが入って来ちゃうと思うのよね。ノブヨシ以降。カメラマンはレンズの後ろ側にいて姿を表さないというゲームを変えてしまったのがあの人だから。それ以降は、写真も当然出るし、川島小鳥さんの顔写真もネットで流通しているこの時代、その土俵には乗らないといけないときに、僕のやるべきこととしては、川島小鳥さんのナイーブな部分が拾いきれない部分について僕が拾いに行く必要を感じている。ある種鈍感だったりとか、メディアで炎上したりだとか、あるいは雑誌だったり広告だったりで仕事をしているから、新しいお金の引っ張り先。新しいマーケットを開拓したりだとか、僕もあまり詳しく無いけど、上の世代をみていると年下に目が行ってないなと思っていて、若い人を育てたり観測している気配がないから、俺はその仕事をきちんとして、若い子たちについて聞かれたときに「◯◯さんと、◯◯さんが良いですよ。おすすめなので仕事投げてみてください」って言えるようにしたい。あ、またアクティビティの話になっちゃったね。

作品としての差別化を言わないといけないよね。そこは俺の弱さなんだと思う。今年はそれをなんとか、穴埋めをしなきゃいけないんだけど、ここ1ヶ月ずっと悩んでいます。あまり思考したり考えたりってのが得意じゃないし苦手だし嫌いだし、ぜんぜん進まないから、ここ2週間やっていることは自分に対する質問文を考えてiPhoneにメモってますね。「私は本当に作品を作りたいのか?」とか。「写真をやるとはいったいどういうことなのか?」「なぜ私は作品が作れないのか?」「私にとって沖縄とはなんなのか?」あるいは「石田の仕事ってそもそもなんなのか?」とか。今はいい答えを得るために、いい質問を考えていますという時期です。
あと今年自分が29歳で、来年30歳なんですよ。なので30歳になるときに何かプロジェクトを仕込めれば40歳になったとき「これ10年やってるんですよ」って言えるから、40歳のステージを見据えるために今年一年考えて次の仕込みの作業をしようかなと思ってます。えっと、何の質問だったっけ?
――差別化の話
そうその話をしてたんだ。差別化としては、今活躍している写真の中で、一番僕は写真が下手だと思っているので、それが一番の強みだと思う。上手な写真って交換可能性があるわけ。下手くそな写真は交換可能性がないので、引き続き写真が下手くそでいきたい。残りの部分を言語化してバッターボックスに立つ必要がありますね、っていう感じです。
――くわえてもうちょっと突っ込みたいんだけど、アートって一般的に使われている「芸術」という意味ともうひとつ「技術」って意味があるじゃない。
特徴ねえ。なんだと思う?
――技術というより被写体との関係性になるけど「不意撃ち」かな。「え、今撮るの!?」みたいな。どういう仕事もそうだけど、ペンキ塗りで例えるならペンキの下地を作る作業。
もちろんもちろん。
――たとえば照明ひとつとっても奥が深そうだよね。
そういうのもあると思う。たとえば「この日でいいのか本当に?」
2つ目は傷つけないってことだよね、やっぱり。
――才能とは違うんだけど、自分の写真家としての嗅覚・
センスとかいろいろひっくるめて、75点じゃん? ってラインだと思う。
――具体的な作業として、こういうのが自分のオリジナルじゃん。
分からない。正直、分からない。よく人からは「何枚並んでても、
――編集の仕方に特徴があるとかそういうことでもないのかな?
うーん、多分無いと思うし、
――人がゆうき君の写真だって分かることに関してはどう思う?
普通に嬉しい。自分の中にも個性があるんだなと思う。自分では分からないけど。
――たとえばこのへんがそれっぽいとか言われたりするの?
そういう細かいところは言われたことない。なんなんだろう。
――ほう!
って喋ってて思ったんだけど。
――何を撮らないの?
赤ちゃんと老人。
――どうして?
退屈だから。そういう写真が嫌いだから。
――子犬は?
子犬も撮らないねえ。
――パンケーキ。
パンケーキ(笑)。パンケーキも撮らないねえ。撮りたいものはなくて、
――逆にさ、積極的に撮りたいものはないってこと?
撮りたいものはないとも言えるし、決めたくないのよね。
撮りたいものでいうと、人間が好きなので人間は撮りたいです。

――それって難しいよね。世の中のお父さんがやってきたことと、や
なんだろう。流通だと思うんだよね。
――ふむふむ、東京に「戻って」きてからゆうきくんが何を考えていたのか、ちょっとだけ理解がすすんだきがします。ありがとうでした。
2018年3月3日@代官山Denny’s
聞き手・写真 吉田俊文
<プロフィール>

石田祐規 Yuki ishida
1989年生まれ。映画監督を目指していたが19歳のとき写真の道へ転向。2010年の「via art 2010」の出展にて写真家デビュー。アートフェア「ULTRA004」にて渋家の全裸の集合写真を30万円で販売。その後は年に数回オンラインでzineを販売している。