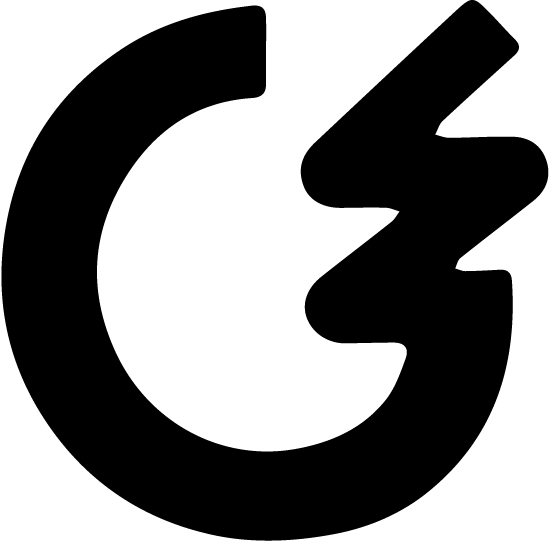第五景
神奈川県相模原市
「パープルーム予備校」
JR相模原駅の改札を出て、駅ビル内に隣接するドトールでガイドを待つ。
コーヒーを啜っていると、まだあどけなさの抜けない顔立ちの女性が、遠慮がちに声をかけてくれた。肩から胸に提げた大きな名札には、筆名だろう「吉田十七歳」の文字。挨拶も早々に、初冬の曇天に覆われた相模原の街路を彼女に先導され歩いてゆく。

ちょうど開催されていた展示『パープルタウンでパープリスム』は、アトリエやギャラリーからなる6ヶ所の会場を巡る、一種のツーリスムのようだった。はじめに案内された3会場は、「パープルーム予備校生」の住居だという。六畳一間の安アパートに、時に過剰に、時にさりげなく作品が点在している。曰く、相模原に住むことが「予備校生」になる条件のひとつだそうだ。


相模原には、果たして何も無かった。
チェーンのラーメン屋、居酒屋、レンタル・ビデオ屋、住居、学習塾、住居、ラブホテル、駐車場、寿司屋、住居、ラーメン屋、駐車場、住居、焼肉屋、駐車場、駐車場、住居……。
ロードサイドの風景が、閉じ込められ、そのままぐるりと包まれて、ひとつの町になったような灰色の市街。そう、相模原はいわゆる郊外都市である。
言うまでもなく、「東京」のオルタナティブ・スペースを紹介する本連載にあって、幾度もの市町村合併を経て、2010年には横浜・川崎に次ぐ政令指定都市となった相模原市は、神奈川県に位置している。しかし70年代以降、

 吉田十七歳が相模原で唯一お気に入りの風景だというビル裏のダクト
吉田十七歳が相模原で唯一お気に入りの風景だというビル裏のダクト
吉田と別れてから、さらに大通り沿いを行くと、鄙びたアパートへ辿り着いた。煤けた居酒屋とラーメン屋が店を構えるすぐ隣には、本展からオープンしたという「パープルームギャラリー」の真新しい白璧がやたらと目に眩しい。換気口から噴出する臭気を抜け、ギシギシと軋む裏階段を上がると、そこが「パープルーム予備校」である。生活と制作が渾然となった空間に、数多の作品が展示されていた。
「何も無いし、治安も悪いし、チェーン店ばっかりだし、あんまり好きじゃないですね、こういうところは」と、パープルーム主催の梅津庸一は苦笑する。
 「パープルーム予備校」
「パープルーム予備校」
 梅津庸一
梅津庸一
パープルームは、既存の美術予備校や美術大学とは異なる、予備校=私塾であり、共同体=コミューンであるようだ。2014年に発足して5年目、毎年増減を繰り返しながらも、現在は5人の「予備校生」とこの近辺に集住しているという。
そもそも、なぜ都心からアクセスが悪く、お世辞にも文化的な風土があるようには見えない相模原を拠点に据えたのだろうか。梅津は「美大が近くだったのもあって、この辺をずっと転々としてきました。その中で、この物件が格安で広かったんです。とはいえ相模原に対して愛着は全くありません」と素っ気ない。「いい点と言えば、どこかの町へお出かけすると他の全てがいい場所に思えるところですね。高円寺とかに住むと、お店が充実し過ぎて遊びにばっかり行っちゃうと思うんですけど、ここは遊びに行く場所がないから、ある意味で活動に集中できる。」
なるほど、隔絶空間で制作に没頭できるアトリエ。ただ、コマーシャル・ギャラリーに所属し、美術館や芸術祭での出品も多い梅津にとって、この場所で展示やイベントを打ち続けることに、どんな意義を感じているのだろう。「何でパープルームをやってるかというと、ギャラリーや美術館に象徴されるような、美術という制度、インフラ自体を信用し切ってないからです」ときっぱりと述べる。「もちろんギャラリーや美術館で発表する機会があったら嬉しいんですが、それらの制度が無くなったらもう“終了”じゃないですか。そこでは誰かからの承認やマッチング、タイミングによってしか展示できない。でもそうじゃないアートのあり方があるはずで、それは自分でやるしかないってずっと思ってきました。」

そして形成されたのが、パープルームというコレクティブだ。「作家個人としてペインティングだけやってると、絵の良し悪しが全ての、アスリート的な主体になってしまいます。でも予備校をやっていると勝手に問題が起きるので、自分本位ではなくなる。実は僕、あまり集団って好きじゃないんです。でも結局、何らかの集団やクラスタには自動的に登録されてしまう。そこで意識的に集団を作れば、本来なら交わらなかったであろう種類や世代の人たちと交流できるんです。」
自覚的に共同体を組織することで、実際に、
その雰囲気とは裏腹に気骨溢れる梅津だが、具体的にはどのような教育を行っているのか。「教育とはちょっと違うんです。僕の知ってることを教えるだけだとマトリョーシカみたいになってしまう。先生—生徒、師匠—弟子という関係ではないんですね。予備校生も僕のことを尊敬してなくて、ちょっとばかにしてるくらい」と笑う。「どっちかって言うとジムのトレーナー。一緒にスパーリングをしながら、“この人と会うと良い”と無理やり人を連れてくる。みんなの作風に僕の影響はないです。とはいえ似てくる部分はあるから、セクト化し過ぎないように、会ったこともないゲスト作家を展示ごとに毎回大量に呼びます。また、予備校の新入生も赤の他人。そういうところでバランスは取れてるんじゃないかな。」

このように運営されるコミュニティは、例えば黒田清輝の画塾・天真道場に代表されるような、近代美術史上の美術運動のシミュレーションでもあるそうだ。「黒田の絵はヘタクソでセンスがないのに、東京美術学校を作ったりして制度設計側の人間になることで、政治的に勝って残っている。今の日本人の絵画って黒田っぽくて、それって悪いことなんですけど、単純に黒田を批判するだけだと自傷行為と一緒になってしまう。それを飲み込んでいく、抱え込んでいくやり方があると僕は思ってます。自分たちが背負い込んで演じ直すことで、全く違う物語が紡げるんじゃないか」と梅津はあくまでコンシャスだ。「美術史には複数の線があります。パッと見、教科書通りに再現してるようで、そうじゃない線も一緒に引く。これはあり得たかもしれない異なる美術史への擬態なんです。」
「ごちゃっとした中から有象無象が出てくる」60年代的な「前衛」のシミュレーションでもあるというその実践の一方で、新設された「パープルームギャラリー」では、ゲスト作家による“パープルームらしくない”端正な展示が開かれ
 「パープルームギャラリー」外観
「パープルームギャラリー」外観
では、アトリエやギャラリーも含め、パープルームという共同体はこれからどうなっていく見通しがあるのだろうか。「それは特に無くてですね」と嘯くも、「パープルームは遠い見通しやビジョンを描いてそれに向かっていくのではなくて、構成する組織の一個ずつの点が集積して、ひとつの形になるタイプ。自分の絵とも通じます。ちょっとした差異や解像度の高い情報をつなぎ合わせて、どういう形や場所になるかは二の次、三の次。そんなマルチエンディングの歴史をプレイしていきたいんです」と梅津は力強く語った。

予備校を後に、すっかり夜の帳が下りた相模原の街を駅へと向かう。往路では殺伐と感じられた地域なきツーリスムが、しかし復路において、どこか体温を帯び始めた。郊外の中でひっそりと、隠れるように息づく「パープルタウン」は、点と点を結ぶことでかろうじて立ち現れる、幻影の町なのだろう。

<パープルーム>
<著者プロフィール>

(c)Taro Inami
中島 晴矢(なかじま はるや)
Artist / Rapper / Writer
1989年生まれ。主な個展に「麻布逍遥」(SNOW Contemporary)、グループ展に「ニュー・フラット・
webサイト