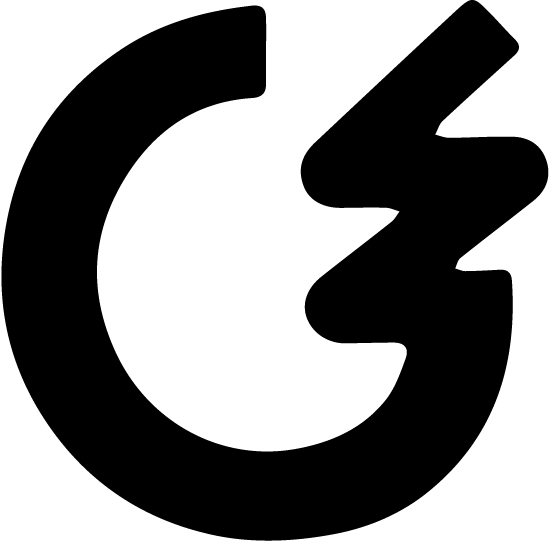第四景
東京都新宿区歌舞伎町
「砂の城」
歌舞伎町一番街アーチは、まるで盛り場の鳥居である。
神社の鳥居が俗世と聖域の境界だとすれば、ギラギラと原色に輝くそのアーチをまたぐと、俗世から、さらに欲深き俗域へと誘われるかのようだ。眼前一杯に氾濫する電飾と喧騒は、この繁華街の下品なまでのダイナミズムを余すことなく伝えてくれる。
ただ、表面的にはこの界隈も、幾分かマイルドになったように見受けられる。ごった返す人間たちの多くが物見遊山の外国人観光客で、ひときわ目を引く「ロボットレストラン」の店頭は、人工的なオリエンタリズムによってカラリと明るく飾り立てられている。コマ劇場跡地に建てられた、新宿東宝ビルから覗く巨大なゴジラの表情にも、どうやら後ろ暗さは浮かんでいない。
 Photo by Mai Shinoda
Photo by Mai Shinoda
さらに奥へと進んでいくと、しかし、昭和の湿り気が徐々にいや増してくる。ある横丁の入り口でその湿度は飽和した。「思い出の抜け道」と掲げられた看板、このさらなる鳥居をくぐると、今度は俗が突き抜けて聖へと反転するように、ほんものの参道みたく薄暗い路地が待っている。真新しい呑み屋のフェイクの提灯を横目に抜けて、見るからに怪しげな雑居ビルのぼろぼろの扉に手を掛ける。酔っ払っていたら確実に転げ落ちるであろう狭く急な階段を登って、3階、そこが芸術公民館跡地「砂の城」である。
 Photo by Mai Shinoda
Photo by Mai Shinoda
「この通りだとウチが一番古くなっちゃったね。表の店なんて出来て一ヶ月も経ってない。邪魔くさいよな。あんまり派手にやるなよ、こっちはこっそりやってんのにさ」と豪快に笑うのは、「屍派」家元の俳人・北大路翼だ。
 北大路翼 Photo by Mai Shinoda
北大路翼 Photo by Mai Shinoda
こじんまりした城内には、雑多なチラシや装飾が所狭しと貼られ、湾曲した銀色のカウンターを中央に、酒瓶と割りもののペットボトルが並んでいる。「だいたいいつもここ」だというカウンター奥に陣取った北大路が手にしているのは紅茶ハイだろうか。私のグラスにも、キンミヤ焼酎でつくった濃い緑茶ハイを注いでくれた。
 Photo by Mai Shinoda
Photo by Mai Shinoda
もともと、美術家・会田誠が2011年に設立した文化的サロンスペース「芸術公民館」(以下:芸公)だったこの場所は、3年程前から北大路を“城主”とする「砂の城」に鞍替えしたのだという。
「当時、僕は芸公に好き勝手に溜まってた。ほとんど“芸公の用心棒”だったね。店長代理みたいな感じで、バーテンのやりくりをしたり、運営のやり方を教えたり、女の子ひとりだと危ないからって残ったり」と北大路は回想する。「この間、会田さんの個展(「GROUND NO PLAN」, 青山クリスタルビル, 2018)の中の芸公ブースにも書いてあったけど、『俺は新宿に負けた』ってのが結構本音だと思うね。流石に手に負えなくなった。やっぱり歌舞伎町にいるとトラブルがめちゃくちゃ多いからね。その頃には僕がやってる俳句の色も強くなってたから、場所を引き継いだ形かな。」
 Photo by Mai Shinoda
Photo by Mai Shinoda
そうして始まった「砂の城」は、オルタナティブ・スペースと括ってしまうにはあまりに混沌としている。果たしてここはサロンなのか、バーなのか、アジトなのか、溜まり場なのか……。
「僕の“城”なんだよね」と北大路は明快に答えてくれた。「たけし城もバカ殿もそうだけど、男のひとつの夢として、殿様になる、城主になるってのがある。で、『砂の城』って崩れやすいから、いつ無くなってもいいっていうのがあって。だから、かなりプライベートな僕の遊び場であり、毎日オフ会をやってるサロンであり、部室であり…要するに俺の部屋だよね。」
 Photo by Mai Shinoda
Photo by Mai Shinoda
砂上の楼閣で夜毎くり広げられる午前1時からの「翼の部屋」。そこに集ってくる「仲間」たちは、言うまでもなく多種多様だ。
「こゆきっていう“男の娘”がバーテンをやってた時期はオカマの子が多かったね。それが店を持って卒業して、今はてんぐちんっていう“妖怪”の女の子がブーム。一種地下アイドル的なノリで、彼女の界隈の子たちがよく来てる」と壁に貼られた“チェキ”を指差す。「[このフロアと繋がっている]上の階に住んでる奴もいるし、この間までなんか4人住んでたからね。カップルとオカマと、あと二十歳くらいの風俗嬢。あの狭い部屋で、夏の暑い中4人で暮らしてたんだから」と北大路は笑い飛ばすが、そんじょそこらのシェアハウスも真っ青の、凄まじいカオスぶりである。「最近では横の繋がりもできてきたから、新宿のアングラ系の飲み屋の人たちもよく来るね。ゴールデン街なんかでも『変な飲み屋ない?』って聞かれると、みんなここを紹介してくれるみたい。」
 Photo by Mai Shinoda
Photo by Mai Shinoda
さらに、ここを文字通り“根城”として活動しているのが、新宿歌舞伎町俳句一家「屍派」だ。歌舞伎町を徘徊して句を詠んでは、城に戻っての講評を繰り返す、アウトローな俳人(廃人?)集団である。
 Photo by Mai Shinoda
Photo by Mai Shinoda
「屍派は2011年の冬に、ライターの石丸元章とここで結成した」と、北大路は二杯目の紅茶ハイを手酌した。「俳句の二大タブーは“セックス”と“バイオレンス”。そこが一番楽しいところなのに、歌舞伎町なんか全くNGなわけじゃない。でも、俳句が自然を詠むものだとしたら、人間も自然の一部だっていうのが僕の基本的な考え。歌舞伎町の人間たちだって、ものすごい季節感の中で生活してる。だから、逆にそれを前面的に売りにしていったの。」
そう、北大路はここ数年で句集『天使の涎』(邑書林, 2015)、『時の瘡蓋』(ふらんす堂, 2017)、編著に『アウトロー俳句 新宿歌舞伎町俳句一家「屍派」』(河出書房新社, 2017)と、本を三冊も出版しており、最近ではテレビ出演などの露出も多い。なんと年末には俳句入門を出版予定(左右社)だという。「自分たちの見られ方はかなり意識してたから、マスコミには上手くハマったね。ヤクザもそうだけど、アイコンとしてのアウトローを演じてる部分はあるからさ」と酒を呷る。まさしく“歌舞いている”わけだ。
 Photo by Mai Shinoda
Photo by Mai Shinoda
では、この稀有なスペースを、北大路は今後どうしていきたいのだろう。「まず建物が丈夫になって欲しいね。いつ壊れるか分からない」と見上げる天井には、雨漏りのためビニール傘が逆さに貼り付けてある。「ずっとテレビ局が取材に来てて、ここのドキュメンタリーを撮ってくれてるんだけど、スポンサーは外国。外国人から見ると、こういう汚くて人が集まるスペースってまさに日本的な風景だから、すごく魅力的らしくてね。ここがオリンピックに反対する最後のレジスタンスだよ。」
そう冗談めかすが、物件といい人間関係といい、やっていることも俳句だし、ここはどこか落語に出てくる江戸の長屋みたいだ。「そうそう、長屋意識なんだよね。だから僕は城主ってより大家のご隠居みたいなもんか。来る人たちも、お客というより家族だよ」と北大路は身を乗り出す。「落語で言えば、アウトローって要は与太郎なんだよね。何やっても駄目な与太郎が、たまにいいものを創ったりするってのが一番面白いところでさ。僕がやろうとしてるアウトロー俳句って、与太郎俳句でもある。」
 Photo by Mai Shinoda
Photo by Mai Shinoda
「あと、活動するにはやっぱり場所が要る」と北大路はオルタナティブな場の重要性を語った。「昔は公園とか銭湯がそうだったけど、今はそういう機能の所ってあんまり無いじゃない。全部ネット上のバーチャル空間になっちゃってるから、それを全部ひっぺがして、リアルな対面の人間関係に戻す為にも、場所は必要だね。」
とはいえ、北大路はSNSも徹底的に活用して句を詠んでいく。一人称が「つばつち」であるように、かねてから気になっていたTwitter上で旧仮名を使う意図を聞いてみると、「あれはキャバクラでウケるんだよ」とトボけつつも、「例えば“おり”ってのは“をり”じゃなきゃ気持ち悪くてさ。僕は手紙の時は漢字も全部旧字で書くの。今の漢字や仮名は国が決めたものだから、勝手に文字を変えられたことに対する怒りもあるんだよ。生理的に受け付けないね、何でもかんでも今の新しい表記にしちゃうのは」と真意を吐露してくれた。
 Photo by Mai Shinoda
Photo by Mai Shinoda
途中から綺麗な女装の方がバーテンをされていたが、取材を終える頃にまた別の女装客が入ってきた。早速北大路と絡んでゲラゲラと笑い合う。そうこうしているうちに若い一組の男女も来訪した。
「一回開いちゃった場所だから、責任持って守っていきたいってのはあるね。ここを頼りにしてる人がいるから、それが筋かな。こうなっちゃうと、もう僕だけのもんじゃないから。」
二杯目の緑茶ハイを飲み干して、彼・彼女らの哄笑を背中に浴びながら店を出る。崩れやすい「砂の城」だろうが、この蜃気楼のような雰囲気のまま、ずっとなくならないで欲しいな、と歌舞伎町の雑踏を歩きながら思った。
 Photo by Mai Shinoda
Photo by Mai Shinoda
<砂の城>
http://shikabaneha.tumblr.com/
<著者プロフィール>

(c)Taro Inami
中島 晴矢(なかじま はるや)
Artist / Rapper / Writer
1989年生まれ。主な個展に「麻布逍遥」(SNOW Contemporary)、グループ展に「ニュー・フラット・
webサイト