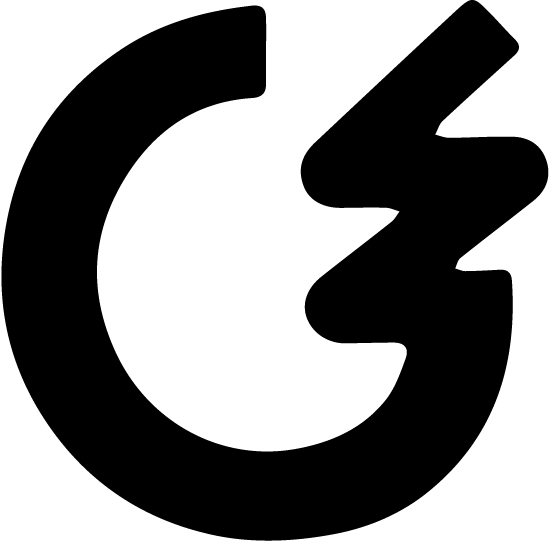木皮成は奇妙な振付家だ、と考える。カンボジアでダンス講師をして日本に帰ってきた彼は、演劇・映像・アイドル振付師などあらゆるジャンルで勢力的に活動していると思いきや、映画「幕が上がる」に役者として出演して人々を驚かせたりする。TOKYO HEALTH CLUBの「supermarket」のMVでは、工事用重機の振付を担当し、「振付という概念」を拡張させているように見える。そんな彼の生活や人生について興味を持ち、普段聞けないようなことをインタビューした。
私生活、それからカンボジアでの仕事
──最近引っ越されたんですってね。
練馬の方に。多摩美に行くとき自由が丘で降りかえれる。結局、週2勤務だったんだけど、平均週4はいたなぁという感じ。
──多摩美術大学のどちらのキャンパスで働いてるんですか?
上野毛です。
──多摩美の世田谷キャンパスで先生をやられているんですね。最近はどんなお仕事を?
最近は、豊橋での市民劇があってそれに関わってました。あと1月の後半からインドネシア人と音楽を作れっていう仕事もあって。
──すごい。
なんか自分でもよくわからない(笑) 国際交流基金アジアセンターというところがあって、そこで僕が以前カンボジアに行っていたという話をレポートとして提出してたのね。アジアセンターではカンボジアの情報が必要だったみたいで、送ったらそこで仲良くなって、アジアセンターではストリートダンスの事業とかもあって、意見を出すようなこともしてました。いよいよアーティストとして参加しませんかと言われたのが、ダンスでも演劇でもなく、音楽作りませんか? っていう話で。「NOTES」っていう企画。確かにトラックをいじるみたいのはやってたけど。
──ダンサーだと音楽の編集もできますよね。
打ちのめされたね。音楽の専門知識がないから。ガチのヴィブラホン、木琴のさらにマニアックなもので、木琴の下にモーターが付いてて、モーターを回すと「ファーン」って響かせるような楽器を扱う人と、琴の人と、作曲家と、俺っていうチーム。
──不思議なチームですね。
なにすんのって話なんだけど、向こうから、インドネシアで現代楽曲の作曲をやっている人と、あと、ガムランの現代音楽を混ぜ合わせたアーティストと、あと演劇とダンスと笛吹きをやるアーティストっていう7人と共同生活して、作品を作るっていう。
──共同生活まで。
そうそう。その企画のミソが共同生活っていう。
──それは面白いですね。そのまま3年前のカンボジアの話をききたいんだけど、行くとなったきっかけは何だったのでしょうか?
きっかけは高松さん。
──「DUFF MAGAZINE」の高松編集長ですね。
でも、俺、DUFFの高松さんのことを知らなくて。そのとき俺自身が超仕事がなくて。そのころの収入源がFUKAIPRODUCE羽衣の振付・単発でくる映像系の仕事で、それがパタンと5月に仕事がなくなって3ヶ月ぐらい仕事がまったくないぞって時期で。なんかしら踊りと仕事を組み合わせようってっときに、得意の鬼サーチでダンスの求人をかき集めて、この中から面白そうなのってときに、一番光っていたのが「カンボジアでダンス講師やりませんか?」っていう求人だった。
──よく見つけましたね。ネットに絶対落ちてなさそう。
もしかしたらそんなに話題にはなってなかったんだけど、注目している人は何人かいて。この求人に興味を持ってつぶやいていた人も当時いて。「私はレッスンを持ってるからいけないな。誰かいないかな。」みたいなツイートがあって。それでメールを送って、今日本にいるんですけどお会いできますか? って。その連絡先が高松さんだったの。そしたら「君、渋家にいたの?」みたいな話になって。俺ぜんぜん取材にいってたよって話で盛り上がって。実は近い人だったというのが分かり。高松さんは10年ぐらい前からカンボジアに出入りしていて、そのときは高松さん自身の映画を撮りたくて、それで出入りしていたときに、ボランティアで学校を訪れて。奥さんが音楽をやっている人で、フルートの奏者で、カンボジアの学校で音楽を教えるボランティアをやっていたらしいんですね。
ポル・ポト政権の原始共産主義の強行で知識人がどんどん殺されていって、最終的に残ったのは14才以下の子供ばっかりらしい。末期の虐殺は知識人の他に芸術家と音楽家と、歌手・先生・思想家とかイケメン美女もみんな殺されたらしいので。今のカンボジアの学校のカリキュラムって、国のリーダーを早急に育てなきゃってことで、国語・数学・英語・社会だけなの。
──絞ったんだ。
そうそう。体育・音楽・理科とかはないの。ずっと座学。校庭とかもあるっちゃ、あるけど、体育目的、教育目的で使っているわけじゃなくて。リズム感がまったくなかったりとか。
──へぇー。逆なんだ。むしろ家庭で継承されるのかと思ってました。
殺された人の中にはもちろん伝統民謡家とか伝統舞踊家とかもいるから、文化自体が伝わっていない。もしかしたらアフリカだったらロックのリズムが継承されたりとかするじゃない。お祭りとかで。そういうことも特になく、カンボジアのお祭りってめっちゃEDMが流れてたりとかする。もう、それクラブじゃん! なかなかハードでした。
──これから新しい歴史が作られていくんだ。
カンボジアの子はすごいFacebookが好きだし、で街にいる人って携帯電話を持つじゃん。韓国は芸能を東南アジアに売り込んでいるから、カンボジアのFacebookのコンテンツとかテレビのコンテンツって韓国の番組だとか、韓国のアイドルが多い。
──韓国の番組を買っちゃうわけですね。
そうそうそう。だからK-popとかみんな好きで。韓国はEDMの曲が多いから、そういう曲が流れたりとか。もっとひどいのはそういう教育がちゃんとなってないってことで、権利問題とかも誰も問題意識を持ってないから、たとえばK-popとかのスーパージュニアなりのBigBangとかのサウンドだけ抜き取って、カラオケね。カラオケだけ抜き取って、自分が書いた歌詞で、俺の新しい曲だぜ、みたいな感じでリリースするっていうのとかも、カヴァーとリミックスと創作のグラデーションが分かってない。オリジナルとコピーの。あとインスパイヤとか。そのあたりの境界線が共有されていないから、オリジナルコンテンツを作れる土壌がないことを目にした高松さん夫妻が、カンボジアでダメージを受けているのは別に学校を作ったりとか食料を作れないとかじゃなくて、それも重要だけれど、何か自分たちで作るということ、一番ダメージを受けているのは文化だっていう考え方をしていて。それで自分たちのコンテンツを作れる人材を育てることを始めた。というのが高松さん。
──高松さんとは日本で会ったんだ?
一回日本で会って、1ヶ月後行ける? みたいな。仕事ないから行きます!って。若干怖かったけど、行けちゃったんだよね。
──そこで人生決まりましたね。
ね、面白かったね。おばあちゃんとかすごい反対したけどね。だって、ばあちゃんの世代からすると「地雷の紛争地で~」みたいなイメージが強いから。詳しくは聞かなかったけど、ばあちゃんは俺を紹介するときに「孫は海外とかにも行ってるんやよ」って言うんだけど、カンボジアの名前は絶対に出さなかった(笑)
──へぇ。そうなんだ。
ばあちゃんの世代にとってはカンボジアって危険なイメージの国なんだと思う。
──今は地雷除去もかなり進んでますよね。
そうそう。今は普通に大丈夫。ものすごい田舎にいってジャングルの中に入ってだったら分からないけれど。最初は3ヶ月カンボジアに行って、帰国して、2回目はバトンタッチする先生がいなくなって、また急遽呼ばれて行きました。3回目は自分のリサーチのために行ったんだよね。アジアセンターと帰国したタイミングで繋がりができてたから、それをアジアセンターにまとめる資料も書きながら滞在しようと1ヶ月ぐらい行ってた。
──カンボジアのどのへんに?
シェムリアップ。プノンペンにもけっこう行ったけどね。シェムリアップはアンコールワットがあるところですね。プノンペンは怖いよ(笑)、スラム感ある。

──10年前と比べたら相当近代化されているでしょう。
どうだろう、たとえば一般家庭に冷蔵庫がないってレベルだから。
──電気は通っている?
通ってる。だけど発電所がなくて、タイから買ってたりとか。フローリングじゃなかったりとか、土じゃん! みたいな家もある。村行ったらいわゆる高床式の家とか。トンレサップ湖ってところがあるんだけど。これがね、カンボジアの真ん中にある湖なんだけど、東南アジア最大の湖だったと思う。滋賀における琵琶湖みたいな。これWikipedia情報だからどこまでが本当か分からないけれど、トンレサップ湖で獲られる魚がカンボジアの人たちの4割のタンパク質になっているらしい。
──へぇー。そうなんだすげぇな。命の湖だ。
伝統料理は代表的なのが覚えてるのが2つあって、ひとつは焼肉定食みたいなもの。あとモックモックって呼ばれるバナナの皮にココナッツパウダーとかをまぶしたもの。香辛料ね。ミルクを混ぜ合わせたキナコ状のものを魚とかチキンとかにまぶしてバナナの皮で包んで蒸すっていう。
──高松さんはいまどこに?
プノンペンにいる。首都に場所を移したんだシェムリアップから。教えてた子たちが、カンボジアの携帯会社のCellcaedのアンバサダーになってる。auとかでいうなら仲間由紀恵とかのポジション。
──すごい。10年前から活動している強みにしても、すごい。
すごい。
東京、そして初の全国CMの振付。
──東京に戻ってきたのはいつでしたっけ?
2016年3月とかかな。
──どうでした? 東京に戻ってみて。
なんだろう。高松さんが面白がってたのは「木皮くん、東京戻ったら全能感すごいよ」って言われたこと。俺なんでもできるって一週間が来るよって。確かにそうだった。
──どういうこと?(笑)
「海外にいってそれなりにサバイブして帰ると、俺、なんでもアクティブになれるわっていうタイミングが1週間あって、そのタイミングでいろいろやるのは楽しいよ。」って。
──よく東京に戻ってこれましたね。カルチャーギャップはありました?
その後、カンボジアにい続けるのも人生として面白いかなって思ってたんだけど、羽衣の演出家の糸井さんから「ボブディランがコンセプトのバーがあるんですけど飲みに行きませんか」って誘われ、そこで今年までやってた市民劇に力を貸して欲しいって口説かれたの。
──んー!
それまでアーティストとしての自信もなく暗黒期もあって、3年ぐらい自分の作品を作ることをやめていたんだけど。才能ないと思ってたから。そのときに糸井さんが「絶対才能あるから、やりなよ」って話をされて、そのときの全能感も手伝って、まず劇場を押さえにいったんだよね。前にやったことあるスタッフさんに話をしにいったら、うちの小屋のプロデュースにするからやりなよってことで、2016年の5月ぐらいに「The Way Feels Go」って新作作ったの。それがDE PAY’S MANの立ち上げになるんだけど。今はみんな忙しくなって、1人だけど。この公演が思いのほか好評で、うちの劇場でワークショップやらない? ってのが一気に3つぐらい来ました。
──すごい。
なんか才能あるのかも、みたいな(笑) のを思って、まぁ、3年溜めてたってのもあるけど、それで去年今年は劇場に行っては子供とワークショップをしてたりしてました。
──去年はなにを?
実は3年間、カンボジアに行っている間も人に託してやっていたダンスサークルがあって、毎週金曜日の深夜に、俳優を集めて一緒にストリートダンスをやるっていうサークル。これが80人ぐらいいたの。
──え、それはまったく知りませんでした。
これね、渋家の経験が生きてるの。渋家のフォーマットをサークル化しただけだから。出入り自由で、知り合いの知り合いであれば誰でも参加できて、演劇人であればダンスの講習は無料っていうのを3年ぐらいやってたんだけど、水面下でやるってのが基本コンセプトで。
──全然知りませんでした。
これで演劇界をかなりリサーチできたんだよね。だいたい出会う人って自分の仕事の範囲だからさ、だいたい分かるんだけど、そこの常識になっちゃって輪郭が見えないから、これでだいぶ輪郭が見えて、それの集大成みたいなもの。もうこのサークルはやってなくて、8月に終わらせようっていう気持ちで去年の8月に80人含めて演劇界に投げたものとしては、ダンス上手くなりたい人いますか?みたいな形で。それと公演を掛け合わせるので、びしばしやるので付いて来てくださいみたいな。カンボジアの経験も生かしてやったら、45人の応募があって、本当はもっと厳しくしたかったけど、残ったのは9人になっちゃって。それで公演をやったって形かな。
──どこでやったの?
池袋のスタジオ空洞ってところなんだけど、ひょっとこ乱舞っていう、今アマヤドリって名前の劇団が持ってるるスタジオで、そこの主宰の人が気にかけてくれてって形かな。そういう感じですね、去年は。ダーテラ経由も仕事も多かったから2017年はヘトヘト。
(※ダーテラ=寺田光顕。DE PAY’S MANのメンバー)
──ダーテラさん経由ということはluteでの仕事もいくつか手がけているんですか?
luteはね、2つ手がけた。ダーテラがやりたかった「AFRO PARKER」と、あと「TOKYO HEALTH CLUB」のディレクターは古屋蔵人さん。
──高所作業車のやつですね。
そうそうそう。あれウケるよね。
──あれ、とっても好きです。一度見たら忘れないPVもそうそうないです。
語ればウケるもん。HOEDOWN(ホーダウン)でドローン飛ばしてくれる人がいるんだけど、風が強すぎて飛ばせねぇって言ってた。
──最近のドローンはどんな状況でも飛ばしているイメージはありますけど。
めっちゃ風が強かったんだよね。あれ、どこだっけ、湘南とかそっち系だった気がする。
──現場のオペレーションがとても大変そうだと感じました。
そうだね。楽しかったけどね。
──ダーテラさんとはどういう繋がりだったのですか?
卒業公演を一緒にやってるの。僕の作品のVJがダーテラだった。それで繋がりがあって、ダーテラが藝大の院の卒制とかも逆に僕が手伝った。
(※VJ=ビデオジョッキー。映像を素材としてDJのようにその場で映像を組み立ててお客さんを盛り上げる)
──そこからDE PAY’S MANに繋がって行くんですね。
そう。頭おかしい人だと思うけど、彼、辛抱強いから、すごいよね。あんなに激務な映像の仕事をやっているのに、まだプライベートでも映像好きってのがすごい。「まだ映像の話すんの、お前!」みたいな。
木皮成、デビュー。
──キャリアとして最初に木皮成がフックアップされた仕事をお伺いしてもいいですか?
それはね、ソニー損保のCMの振付だね。
──これがデビュー戦という印象ですね。
そうだね。これもね、僕も若かったし24歳だったから、もう4年前なんだね。キャスティング・ディレクターが演劇好きの方で。その方がよく羽衣を見にきてくれていて、その監督が初めて「踊りもの」を撮るってなったときに「振付師、良い人いない?」ってなって。小劇場でいうと、僕ともう一人挙げてくれていて、プレゼンのし合いみたいになったのね。それでプレゼンの結果、僕を採ってくれたってのがあります。1年放送される予定のCMだったから、すごい嬉しかった。現場では、映画「500日のサマー」みたいにしたいって言われて、それのオマージュが「モテキ」に繋がっていて、そういう系譜があって、「モテキ」が流行ってた時期だったから、それをどう30秒に収めるかというところに腐心しました。そのときスタンドインしてくれたのがダンサーの新庄恵依さん。
──へぇー。
羽衣の大事な公演期間中で、すごいボロボロだったの。青山円形劇場で公演をやってて。そっちはゲネ中で、こっちは撮影で、みたいな。でもやるしかないって感じで。現場は火の車って感じだった。
──映像が特殊だったから、あれはモーションコントロールカメラですよね。シビアな撮影だったはず。
そうそう、それを無事に納品したんだけど、3ヶ月で放映が終了しちゃって。評判が良かったんだけど、いきそうってところで跳ねなかったところだから。
──それは本当に悔しいところですね。
そのあとは暗黒期よ(笑)。強制執行の仕事してた時期があるんですよ。
──ずっと以前に言ってましたね。
すごい大変で、食うことに必死な時期が来て。作品も作ってなけりゃ、お金もない。仲間との不仲もあり、ハート的にも大変だった。決して人当たりのよくない時期にも暖かく接してくれたダーテラはすごいんだよね。
──まるで仏様みたいな人なんですね。
だからダーテラの仕事は俺絶対に断らないもん。ダーテラ困ってるときは助けたいし(笑)。
木皮成、成熟せり。
──木皮成さんは「20代・振付家」というカテゴリーでは最前線を走っていますが、同時にまだ売れ切っていないという苦しみも同時に味わっていると思います。その辺の心境について伺ってもよろしいですか?
メディアの業界と演劇の業界と両輪走らせていることに成功しているのは僕だけだから、そこは大きくて。
──確かに、それを両立されている方となると相当年上の方になりますもんね。
それが今後の強みだろうし、面白いだろうなと思ってて、本当は自分でも作品を作りたいなって気持ちもあって。今はカンボジアで撮ってたストックもあってそれをいつリリースしようかっていうのがある。タイミングを見ているけど。
──今、何をやってもタイムラインに流されちゃうという状況があって、タイミングは難しいですよね。
そうだよね。公演やるってなっても協賛とか、小屋が応援しているとかじゃないと踏み込めなかったり。あと、そのタイミングで熱い仲間がいるかってのが重要。
──グルーヴ感ですね。
バイヤーが乗ってるタイミングか、とか。天文学的なタイミングの難しさ。舞台だと。今は、将来に向けて考えていることは2つで、2020年以降に続けれる体力と、舞踊の世界で倒れないためのシェルターを作る。安全圏にいる、安全圏を確保するってこと。それにちょっと絡んじゃうんだけど、舞踊の研究書を作るっていう。それは自分はストリートダンスをやっているから、大学教育の中の研究分野ってモダンダンス・バレエダンスの世界、もしくは裾野を広げてコンテンポラリーダンス。それは系譜としてモダンだとかバレエの系譜のものが研究対象になっているんだけど、たまたま昨年から教育の場にいるから、今後のことを考えると書籍にまとめたいってのがある。やりたいのがヒップホップカルチャーにおける、舞踊研究というテーマで本を書きたい。
──ヒップホップはキーワードとしても熱いですよね。この前、中国がヒップホップを規制したというニュースも見ました。
今、教育の場にヒップホップを客観視できる人がいないというのもあって、やりたいと思っています。
<プロフィール>
木皮成

1990年、和歌山県 生まれ。
2010年からアジア舞台芸術祭に継続的に参加。
俳優のダンスサークル DAP TOKYO 代表。
多摩美術大学 演劇舞踊デザイン学科 非常勤講師。
DE PAY’S MANの代表・振付プランナー。
「DJみそしるとMCごはん」のMVや、「TOKYO HEALTH CLUB」のMVの振付を手がける。