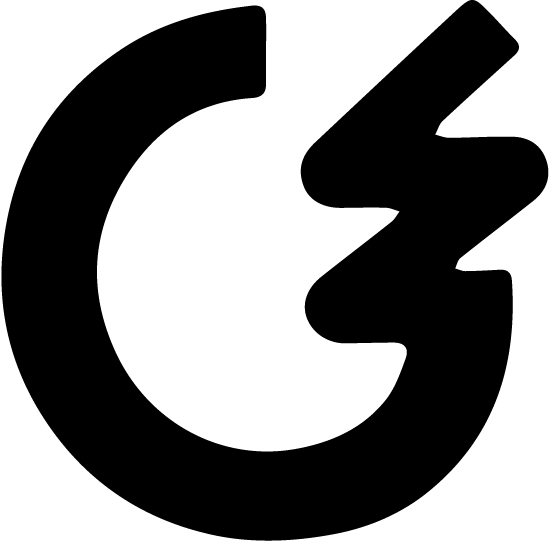著:荒渡巌
夏は猛威を振るう。人類だけにではなく、動物や植物、恐らくは微生物にだってこれほどの酷暑は猛威を振るう。本来ならば、しとしと雨が降る季節だというのに、今年は人々の肌がみるみる小麦色に焼かれてしまうほど鋭く紫外線が降り注いでいる。そのまま梅雨明け宣言をニュースで聞いて呆気にとられた直後に、西日本では大規模な降雨災害がもたらされた。アルプスの山々に囲まれたこの地でも週間天気予報は数時間単位で太陽と傘のマークを入れ替え、明日の作業予定もままならない日が続いた。農業というのは人間相手の商売であるのだが、やはり天地の狭間において成立している生業であることを痛感する。農の世界において、人間はどうしたって風景に点じられた一点に過ぎないのだ。
「田舎の夏」は幼少期に思い描いていたような穏やかな表情ではなく、鉄仮面でも被っているかのような非情さで忍び寄り、気がつけば地上に生ける万物が雁字搦めにされてしまっていた。

とは言え、ヒトも農耕を始めてから2万年以上が経つとのことである。その間、天地とうまく折り合いをつけながら生命を育み、食を繋いできた。そうした創意工夫の絶え間ない連続が今日の農業技術を支えている。
そんな農テクの一つに「根覆い」の技術がある。洋の東西を問わず、稲藁や麦、牧草などを作物の株元に敷くことで、保水性を高めたり、泥跳ねを防止したり、地温の上昇を抑制するという技術が広く農民の知恵として伝承されてきた。こうした土と敷藁や敷草の織りなす牧歌的な風景は戦後になってプラ製品が国内で製造出来るようになってくると、代替技術によって爆発的に置き換えられることになる。「マルチ」の登場である。

「マルチ」というのは外来語である。英語圏においては”mulch”と表記し、「根を覆う」という意味の単語となる。日本では転じて、根覆いを目的としたポリエチレン製のフィルムを総じて「マルチ」と呼び、圃場に敷設することを「マルチを張る」などと言う。
大都市に生まれ育ち、郊外になど出たことがない、出たところで絶景でもない農村風景に目を奪われたりしない人間にとっては馴染みのない光景となるのだろうが、畑作地域を通過すれば、圃場の畝を帯状に覆っている黒いビニールフィルムを否が応でも視界の隅に捉えるはずである。それこそは「黒マルチ」なるものであり、現代農業には欠かせない資材の一つとなっている。
マルチは、フィルムの色によってその効能が違ってくるのだが、基本的には地温の調整、雑草の防除、保水性確保、土壌の流亡阻止などが主な機能となっている。特に雑草の防除や地温上昇(!)という点では、敷藁や敷草などでは代替の効かない、唯一無二の効果を発揮してくれる。
このような資材を適切に使用すれば、元来日本の風土に適さない作物(市場に並んでいる野菜の九割以上は日本に原種が存在しない舶来品)を畑に出しても、生育に最適な環境を整えてやることも出来る。つまり作物にとっての「自然」を擬似的に創出することができるのだ。まるで良いこと尽くめのようである。
では「マルチ万歳!」ってこと?というと話はそう単純ではない。そもそも畑にめっちゃ黒い筋が入っているのはめちゃくちゃ不自然な気がするし、景観的にも全く美しいとは感じられないのでは?農に関わる前はそんな風に考えていて、この大層便利で現代的な資材のことをあまり好ましく思っていなかったものだ。

その否定的な感覚は農のド素人であるが故の食わず嫌いであった、農業で金を得るならマルチ一択!──となれば話は簡単なのだが、そうもいかない。一部の営農者にとっては、マルチとどう向き合うかというのが悩みの種となっている。何故かなら、このポリエチレンのフィルムは完璧に回収することが難しく土中に残留し続け、また回収された部分もその多くが産業廃棄物となり再生産の循環から外れてしまう。要するに環境負荷の高い資材だからである。
トラクターの回転刃を入れて畑を耕せば地表にベロリと、だらしなく顔を出すものがある。マルチの切れ端だ。ポリエチレンは分解までに数百年かかるとも言われており、それも分解に好適な環境下においてであろうから場所によっては千年単位で残留することもあろう。土器や道具の破片なんかが発掘されれば遠い未来のヒトによって博物館や研究機関に収蔵されるということもあり得るだろうが、ビラビラの切れ端が番号を振られて鍵付きの防湿庫に保管されることは非常に考えづらい。これは未来においても確実にゴミだ。まさにゴミの中のゴミ。ゴミ王。
先述の通り、農業というのは人間相手の商売であるから、効率的に商品作物を生産しようとするならばマルチを張らない選択はありえない。だが、天地自然との繋がりのなかに農がある、と考える農業者にとって、一人の人間の選択によって土壌に痕跡を残し続けるというのはどこか過剰であるように感じるのだろう。実際に、化学肥料や農薬を使用しない、と決断した志ある農業者の中には、このマルチを頑なに使用しないという信念を貫き、そのまま営農を挫折する者までいると伝え聞く。理想と現実がままならぬのはどの業界も一緒であるが、強い志を持って農業に挑戦する人間が、その志の高さゆえに生活を追われてしまうという事実を突きつけられると、小皺の増えそうな表情になってしまう。
マルチが掛けられた風景というのは現代的なヒトの営みそのものの、ハードコアな戯画であるようにも思える。自然農を謳いながらマルチを張る。有機栽培と謳いながらマルチを張る。そして我々消費者は部分的な美談に酔いしれて「食材」を購入する。マルチの有無なんて知ったこっちゃない。農村では風景を切り裂くように線が走る。マルチが大地を走る。本質的なものを覆い隠すように。もしくは暴き出すように──

じゃあ荒渡巖は自分の借りている圃場ではどうしているの?という疑問があるかも知れないので答えておくと、私はマルチを張ることにした。マルチを張らないことは、作物以外の植物(雑草)と日々対決し、手作業で除草しなければならないということを意味する。(草の中でも作物は育つかと言えば育つが、まともな「出荷」は出来ない。)平日は毎日フルタイムで研修先に拘束されていることを考えると、マルチ無しではとてもじゃないが管理がしきれない。ということで現実的にマルチを張ることになったわけだが、やはり人様の土地の土中にしょうもないゴミ、ゴミ王が蓄積されていくというのは非常にバツの悪い思いがする。産廃にするのも何かが違う。そこで、廃マルチを使って何か作れないかと考えるようになった。
最近は専ら農作業に従事しているので現代美術家としての制作活動に専念する時間は取れないが、それでも依然として芸術の魔術的な力を信じている。合理的、経済的な判断だけではどうしても帳尻が合わない現場から芸術行為というのは自然発生する様な気がしているのだ。どうせなら自生えの芸術がみてみたい。マルチへの割り切れない思いは、何か別のモノに突然変異しそうな予感がする。技量が足らず全く作品として結実しないのかも知れないが、それはそれでまた新たな葛藤を生み、次なる一手の種となる。
ヒトとして生きていく本質を手繰り寄せるような農活の中で、それでも虚構や幻想に手を伸ばしたくなる時、また世の中の創作物のどれもがその現実を慰められない時に――渇望してしまうヴィジョンがあるのなら、私はそれを活写しようと思う。それはきっと、私にとってもあなたにとっても、特別な景観であるはずだから。
荒渡巌 Iwao Arawatari
Twitter

1986年東京育ち。2017年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了。SNSのコミュニケーション空間やディスプレイに投影される画像がもたらす特殊な体験に傾注し、制作を行っている。サロン・ド・プランタン賞受賞。主な展示に「転生 / Transmigration 2015」Alang Alang House(ウブド)、「カオス*ラウンジpresents『怒りの日』」(いわき)などがある。若手芸術家による実験販売活動「カタルシスの岸辺」の店長でもある。2018年3月より長野県某所にて農業研修中。